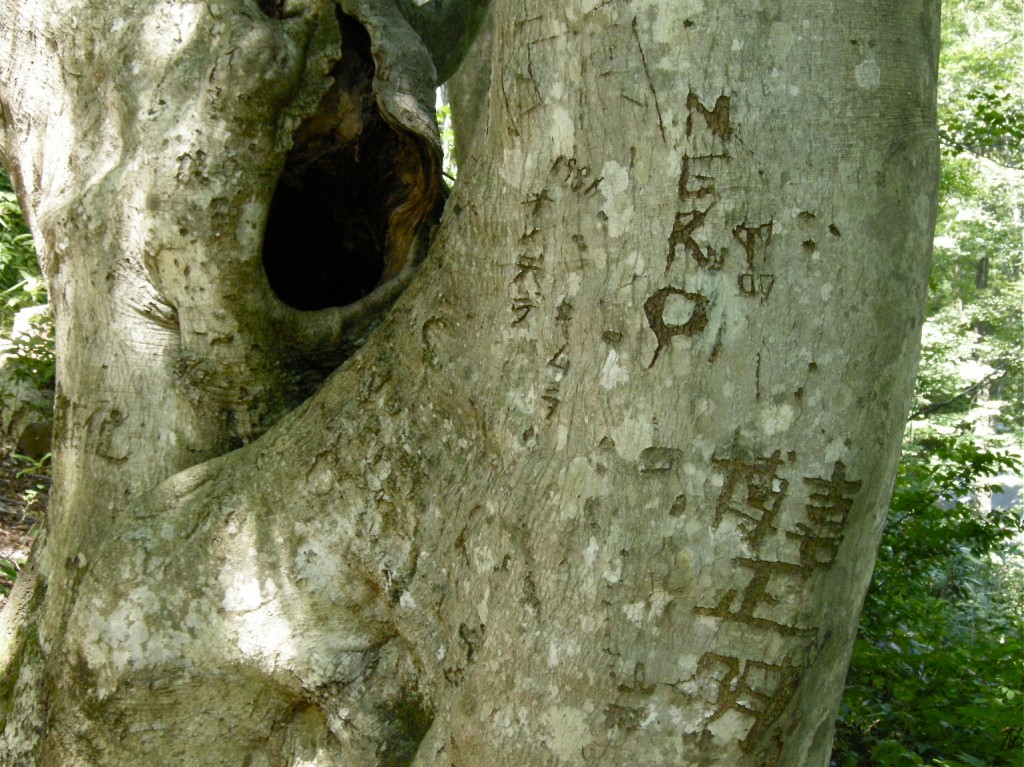工事中の住宅の屋根は瓦葺きですが、台風など風雨がたいへん強い場合は風圧によって瓦の合わせ目から裏に水が侵入することがあります。そうした時に建物内に雨が漏らないようにするための屋根用の防水シート=ルーフィング(roofing)を屋根全面に施します。
写真の灰色にみえているのがそのルーフィングで、フェルト状の原紙にアスファルトを浸透・皮膜し、さらに癒着や滑落を防止するために表面に雲母粉などを付着させたものです。昔はほんとうにただのぺらぺらの黒い紙みたいで頼りない感じでしたが、現在のアスファルトルーフィングは通称「ゴムアス」といっていろいろと工夫改良されています。アスファルト自体がポリマーなどを含有し(改質アスファルト)寒暖の影響を低減し、また弾性があるため破れにくくステープルや釘打の穴に対する防水 シール性を増しています。
軒先と平行に多数横に並んでいる細い木は瓦を止める瓦桟ですが、縦に並んでいるのは流水テープといってルーフィングと瓦桟との間にすこし隙間を設けて、瓦桟に水が溜まらないようにするためのものです。以前であればキズリといってこれも木の桟でしたが、いまは樹脂製。瓦桟とこの流水テープが交差したところで屋根の垂木に釘止めします。