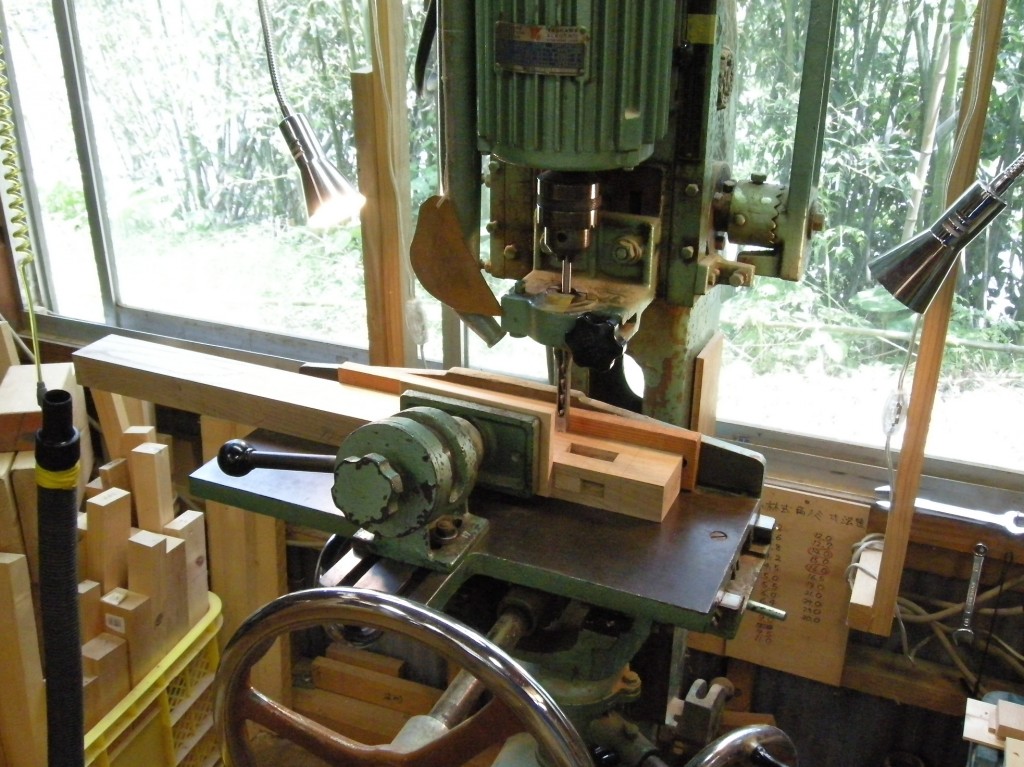酒田市内の某宅で、3日前からトイレの改装工事をしています。これまではトイレと手洗の部分が引き戸で仕切られて別室になっていたのですが、これを一室にまとめる工事です。それにともなって便器と手洗器、照明、ドアなどを新調します。
まずは便器等を取り外し、既存の天井・壁・床を下地材を含めてすべて解体撤去しました。このトイレは建物の内部に位置していて野外に面した窓がないのと、日中も普段通りにお客様が生活しながらの工事なので、極力騒音と粉塵を発生させないようにしながらの作業です。通常のリフォーム工事であれば、多少の釘やビスなどは木材といっしょに切断してしまえるようなタイプのチップソーを装着した丸ノコで一気に片付けてしまうのですが、それだともうもうと粉塵が出て建物中がほこりまみれになってしまいます。そのため解体はすべて手作業で行いました。
石膏ボードや床板のフローリング、コンパネ、下地・骨組の木材などをすこしずつ手ノコで切ったのですが、ごらんのとおり歯がぼろぼろ。20個くらいの歯が折れてしまっています。それを予想して替え刃式のノコで、釘等に気をつけながら作業したのですが、表からは見えない釘も多く、どうしてもある程度はかじってしまいました。刃1枚が1000円くらいの替え刃式ノコだからいいようなものの、これが固定刃だったら泣いてしまいますね。