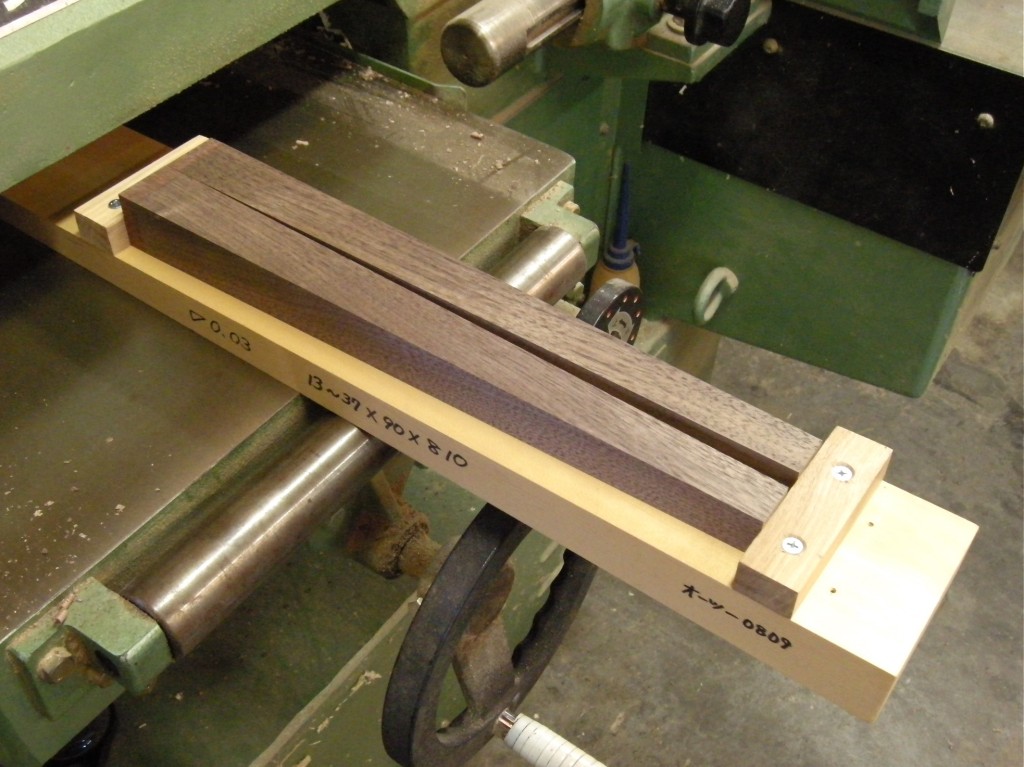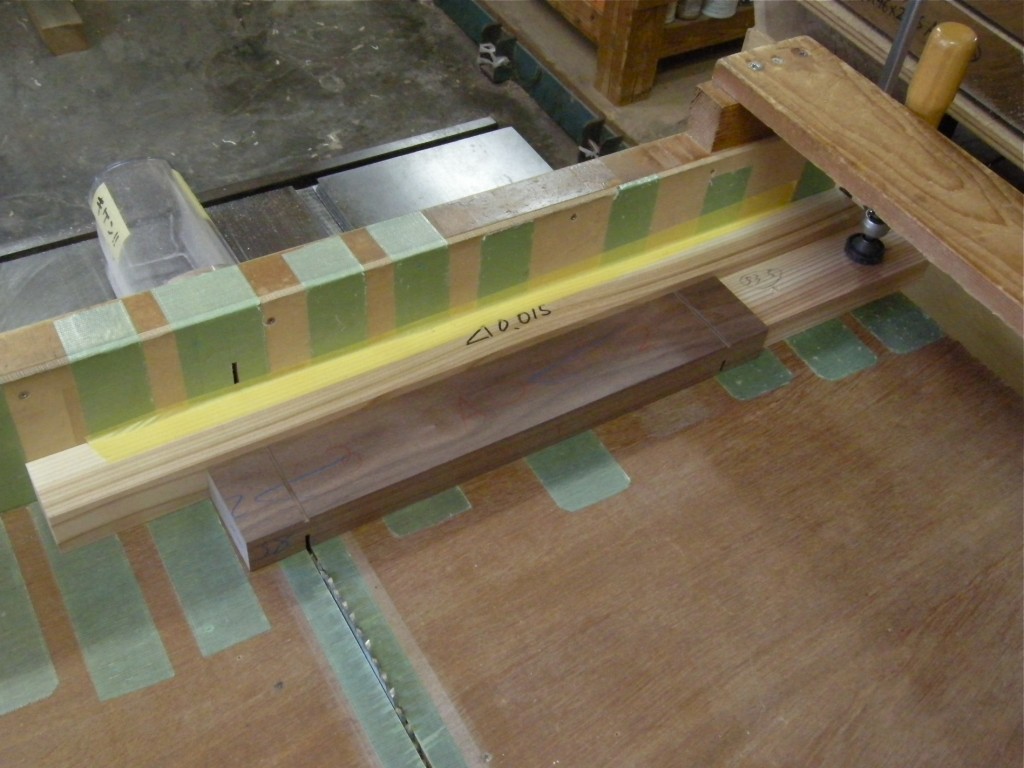7月29日に鳥海山に登りました。コースは、妻と子供は別行動で鉾立から御浜の往復。私と、妻の知り合いの女性の方お二人との3名パーティーは、大平〜御浜〜文殊岳〜御浜〜鉾立です。私たち3人は朝5時半に歩き始め、夕刻5時に下山という、休憩も含めてですが12時間近い山行でした。
しかしずっと心配し半ば覚悟もしていた雨は、昼過ぎと夕方にすこし降っただけで、むしろおおかたは薄曇りで涼しく過ごしやすかったです。とりあえずの目標の山頂までは至りませんでしたが、じつにたくさんの花に出会うことができ、女性お二人も大満足の山行となりました。のんびりゆっくり美しい花と景色を愛でながらの山旅です。他人と競ったり、脇目もふらずにしゃにむに歩くのは逆にもったいなさすぎます。
私がいちおうわかった花だけでも80種もあるので、わかりやすいように50音順に並べます。青色の種は写真も下に載せました。ただし私は植物の専門家ではありませんのでもしかしたら間違っているものもあるかもしれませんし、写真も安いコンパクトデジカメでざっと撮ったものなのであまり写りはよくないです。
咲いていた花=アオノツガザクラ、アカモノ(イワハゼ)、イブキゼリモドキ、イワイチョウ、イワオトギリ、イワカガミ、イワテトウキ(ミヤマトウキ)、イワブクロ、ウゴアザミ、ウメバチソウ、ウラジロヨウラク、エゾウサギギク、エゾノヨツバムグラ、オオバキスミレ、オオヤマサギソウ?、オクキタアザミ、オンタデ、カラマツソウ、ガンコウラン、キバナノコマノツメ、クガイソウ、クルマユリ、クロヅル、コシジオウレン(ミツバノバイカオウレン)、ゴゼンタチバナ、コバイケイソウ、コメバツガザクラ?、シラネニンジン、シロバナトウウチソウ、シロバナハナニガナ、ズダヤクシュ、タカネアオヤギソウ、タチギボウシ(コバギボウシ)、チョウカイアザミ、チョウカイフスマ、ツクバネソウ、ツルアリドオシ、ツルリンドウ、チングルマ、トウゲブキ、ニッコウキスゲ、ネバリノギラン、ノウゴウイチゴ、ノリウツギ、ハクサンイチゲ、ハクサンシャクナゲ、ハクサンシャジン、ハクサンチドリ、ハクサンフウロ、ハクサンボウフウ、ハナニガナ、ヒトツバヨモギ、ヒナザクラ、ヒヨドリバナ、ベニバナイチゴ、ホソバイワベンケイ、マイヅルソウ、マルバキンレイカ、マルバシモツケ、ミズキ、ミネカエデ、ミヤマアカバナ、ミヤマアキノキリンソウ、ミヤマウスユキソウ(ヒナウスユキソウ)、ミヤマキンバイ、ミヤマクロスゲ、ミヤマコウゾリナ、ミヤマシシウド、ミヤマダイモンジソウ、ミヤマツボスミレ、ミヤマハンショウヅル、ミヤマホツツジ、ミヤマリンドウ、ヤマガラシ、ヤマハハコ、ヤマブキショウマ、ヤマホタルブクロ、ヤマユリ、ヨツバシオガマ、ヨツバヒヨドリ

チョウカイアザミ(キク科)と鳥海湖。後方右は鍋森、左は月山森