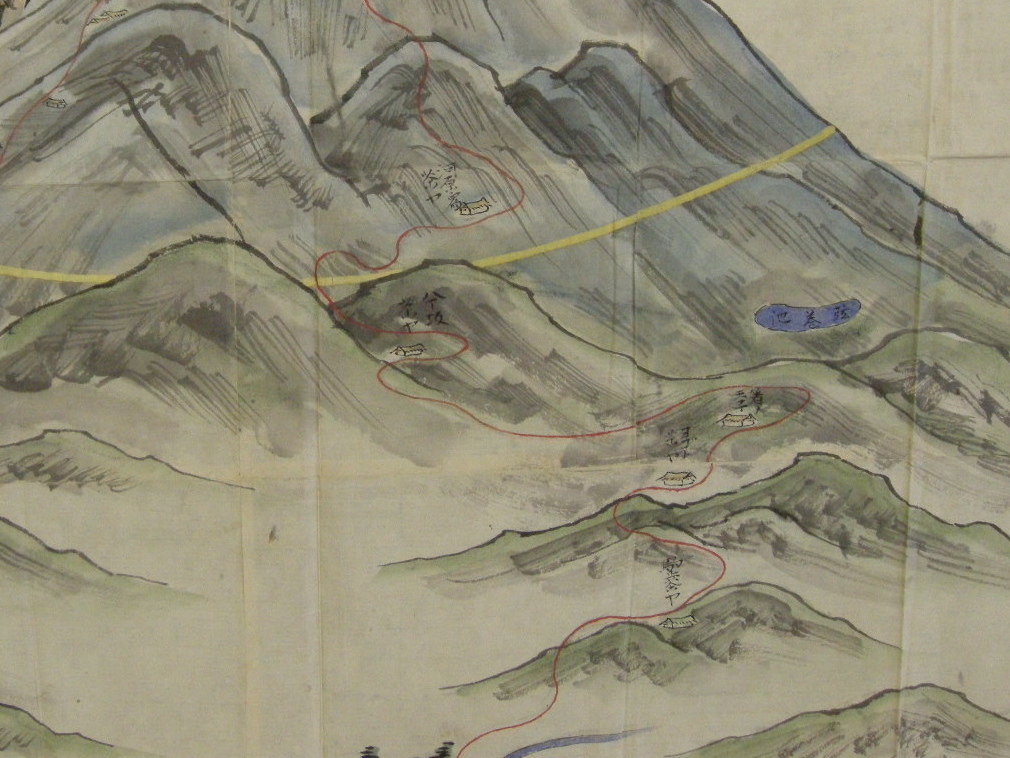工房の敷地は入口付近のごく一部をのぞいて舗装されていません。したがってとうぜんながら草がどんどん生えます。ほうっておくと草ぼうぼうのまるで廃工場のような外観になってしまうし、周囲がいつも湿りがちになってしまうので建物にも悪影響を及ぼします。蚊なども発生しやすくなります。それで5月末頃から8月中頃まで5、6回ほど草刈りをします。先日(6/14)はその2回目でした。
以前は大きな草刈り鎌で刈っていたのですが、今は自分もだんだん年をとってきて体力の限界を感じてきたため機械で刈っています。一般には「草刈機」と呼ばれることが多い機械ですが、草だけでなく竹や小灌木なども切ることができるので、正式には「刈払機」と呼ぶようです。私が使っている刈払機はマキタのMEM426という機種ですが、4ストロークの24.5mlの無鉛ガソリン(レギュラーガソリン)仕様のエンジンで駆動します。
世間一般では2ストローク(2サイクル)で混合ガソリンを使うエンジンのものが多いように思いますが、それに比べると燃料代はおよそ半分、排気ガスは90%減。低騒音ですし、燃料に潤滑油を混ぜないのでキャブレタが詰まりにくい、などの利点があります。4サイクルの刈払機は2サイクルの刈払機に比べると値段はすこし高目のようですが、実際使ってみればじゅうぶんそれだけの価値はあります。MEM426は定価で5万ちょうどくらいだったか。
刈払機を日頃使われている方はよくご承知のように、じつに便利ですが同時に非常に危険な機械でもあります。手順を守って慎重に作業をおこなえばいいのですが、機械のメンテナンスを怠ったり、いい加減な体勢や気持ちで刈り払いをしたりすると大怪我をするかもしれません。自分が怪我するだけならまだしも、他人を傷つけたら最悪です。
刃は刈払機専用の刃を用いるのですが、刈る対象の違い(草か灌木か竹か、軟質か硬質か)や刈り残しの程度や作業条件などによって、じつにたくさんのタイプの刃があります。私が使っているのは木工用のチップソーの刃に似たギザギザの刃(写真中)と、2本のナイロンコードの刃です。前者は回転刃が石等に当たった際に刃先端のチップが欠けにくいように特殊なろうづけをしてあることや、できるだけ軽くするためにベースがスチールではなくアルミ合金であったり、たくさん窓が開いていたりします。切れなくなったら電動丸ノコの刃と同様に研磨屋さんに研いでもらいます。再研磨しない(できない)安価な使い捨ての刃も売られていますが、私は使いません。
後者はドラム内部に径3mmほどの長いナイロンの無垢の紐が組み込まれているもので、遠心力によって必要な長さ(10cmくらい)が半自動的に繰り出されるようになっています。柔軟性のあるコードなのでフェンスや庭石や建物のごく近くまで草をほぼ完全に刈りとることができます。ただ切断するというよりはものすごい速度でばしっと力任せに草をなぎ倒すといったほうがいい具合なので、草の汁や粉砕された葉や茎があたりにけっこう飛び散ります。コードは単純な丸断面のものから、螺旋をえがいているもの、ギザギザのフックがあるものなどいろいろです。ただ丸いだけのものより、後者の異形コードのほうがもちろん性能はいいです。
刈払機は本体をベルトで肩から吊るすか、背中に背負うのですが、長時間かつ日常的に高頻度で使うのであれば背負式のほうが楽でいいでしょうね。私のは肩から専用の付属ベルトで吊るす式ですが。また刃以外にも、さまざまな形状のハンドルや、ノコ刃が地面に接触しにくくするための補助器具(中の写真の赤い部品)、回転軸に巻きついた草などをさらに切り落とす刃、丈の長い刈り取った草をまとめて脇に寄せるためのガイドなど、多種多様な付属品が市販されています。刃やそれらの付属品をそのつど交換するのは意外に面倒で、微妙なセッティングが必要な場合が少なくないので、農家など刈り払いのプロは刈払機を最低2台は持っているようです。
※ MEM426は現在廃番で、後継機種はMEM427、またはMEM427Xです。マキタには最新式では36Vのリチウムイオンバッテリーで駆動する刈払機もありますが、値段は電池+充電器+本体のセット定価108000円(税別)。しかしランニングコストは4サイクルガソリンに比べても約1/10で、もちろん低騒音、メンテナンスも楽。車と同じで近い将来は充電式刈払機が主役になるかな。