 これは俗に「世界最大のネズミ」とウワサされるカピバラです。大型犬くらいの大きさがあり、ネズミというにはおどろくべき巨体ですが、たしかに顔のあたりの雰囲気はネズミに似ていなくもないですね。
これは俗に「世界最大のネズミ」とウワサされるカピバラです。大型犬くらいの大きさがあり、ネズミというにはおどろくべき巨体ですが、たしかに顔のあたりの雰囲気はネズミに似ていなくもないですね。
保育園のバス遠足で先日、秋田市の大森山動物園に行ってきました。トラとかゾウとかキリンなどの目玉の動物もさることながら、もうひとつのお目当てがこのカピバラ。正午すぎで気温も26℃にもなったらしいので、屋外の日向のカピバラはどてっと横になって寝ていましたが、室内にいたカピバラはごらんのように静かにたたずんでいました。
カピバラは体長105〜135cm、体重も35〜65kgにも達するそうで、ネズミ目(齧歯目)では最大。分類としてはヤアマラシ亜目カピバラ科カピバラ属カピバラ(Hydrochoerus hydrochoerus) で、カピバラ属の唯一の種。思いのほか珍しい動物のようです。ただ大きいだけのネズミではなかったんですね。性格がとてもおだやかで人になつきやすいため、ペットとして飼っている人もいるそうです(秋篠宮も飼われておられるとか)。



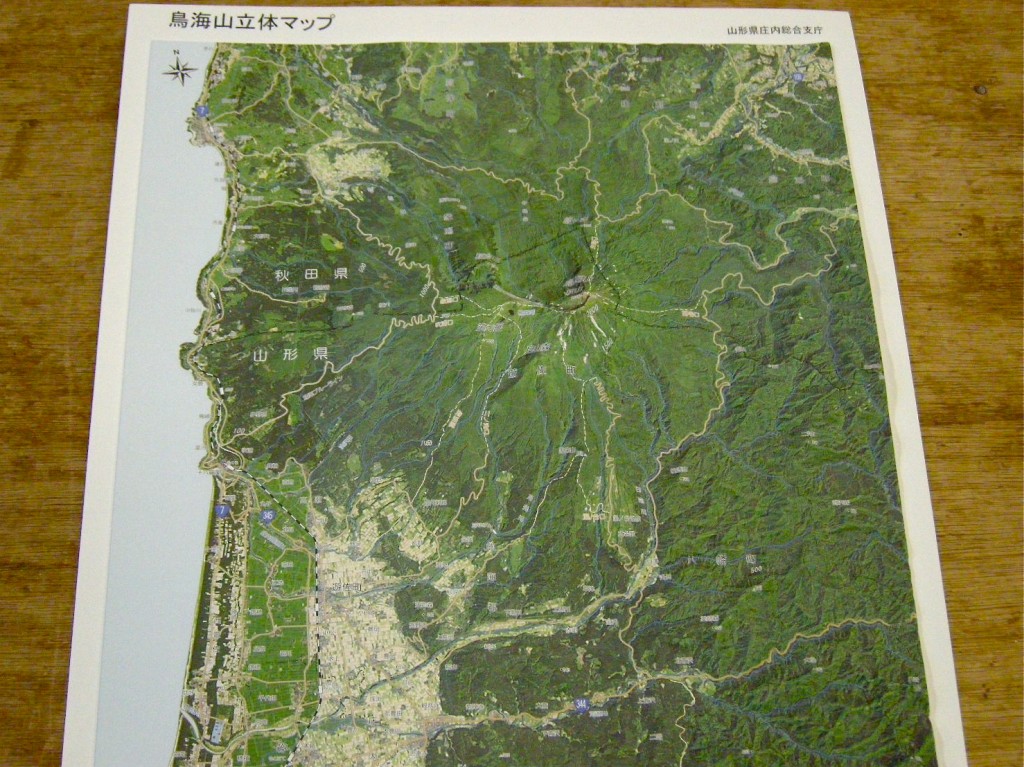

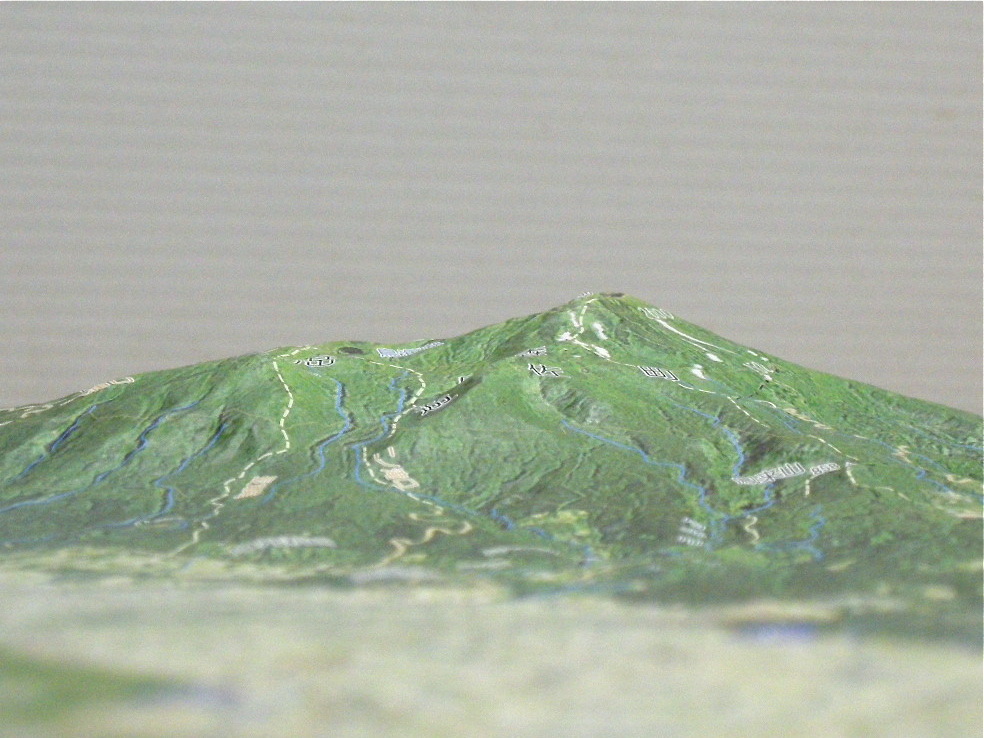








 上の写真は5月11日の午後5時13分、下の写真は5月18日の午前8時33分に撮ったものです。湧出水量としてはほぼ同じくらいですが、上のほうがわずかに多いでしょうか。水温は11日が右8.9℃、左も8.9℃です(気温12.3℃)。18日は右が8.8℃、左が8.7℃でした(気温10.8℃)。18日の温度は5月3日ならびに4月25日とまったく同じです。
上の写真は5月11日の午後5時13分、下の写真は5月18日の午前8時33分に撮ったものです。湧出水量としてはほぼ同じくらいですが、上のほうがわずかに多いでしょうか。水温は11日が右8.9℃、左も8.9℃です(気温12.3℃)。18日は右が8.8℃、左が8.7℃でした(気温10.8℃)。18日の温度は5月3日ならびに4月25日とまったく同じです。