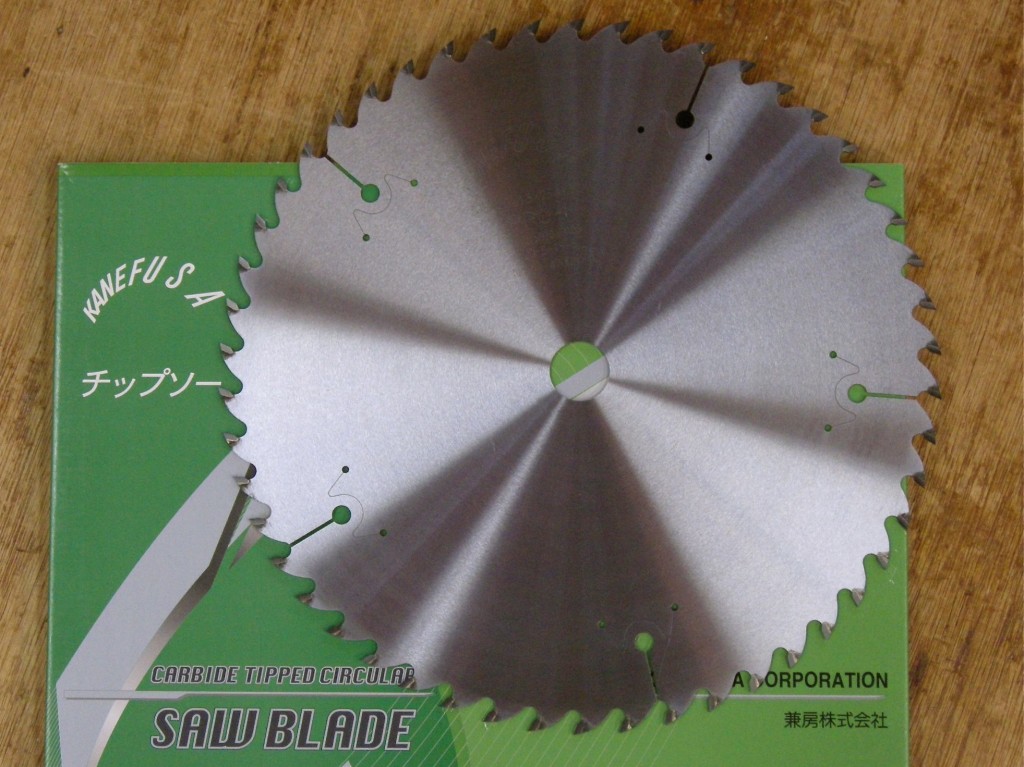12月28日の午後6時すぎに父が死亡しました。食べ物の誤飲から呼吸不全、そして心不全となっての急死です。91歳の誕生日を間近にしてのできごとでした。
4年以上施設に入所し、今年になってからだけでも誤飲や肺炎などで何度も救急車で病院に運ばれていました。そのたびに目にみえて体力の低下をきたしていましたので、兄弟・親族は覚悟していたとはいえ、やはり実際にそのときになってみるとうろたえ悲嘆にくれ、たいへんでした。それでも30日に通夜、そして大晦日の31日の今日が葬儀と火葬で、なんとか正月前に一区切り終えることができました。
父は自分の代一代で会社を立ち上げ築いてきた人間で、私の木工業に対しては心配しながらもたくさんの助言や協力をしてもらいました。けんかもしましたが、なにもないところから非常な苦労の末に、それなりの技術者・経営者となりえたという点で、私と父とは深く共鳴するものがあったように思います。
しかしながら残念なのは、父の期待に十分にはこたえることができていないことです。
今回の父の死を、ひとつの道標として、今後もより高みをめざしていくつもりでいますので、今後ともなにとぞよろしくお願いいたします。