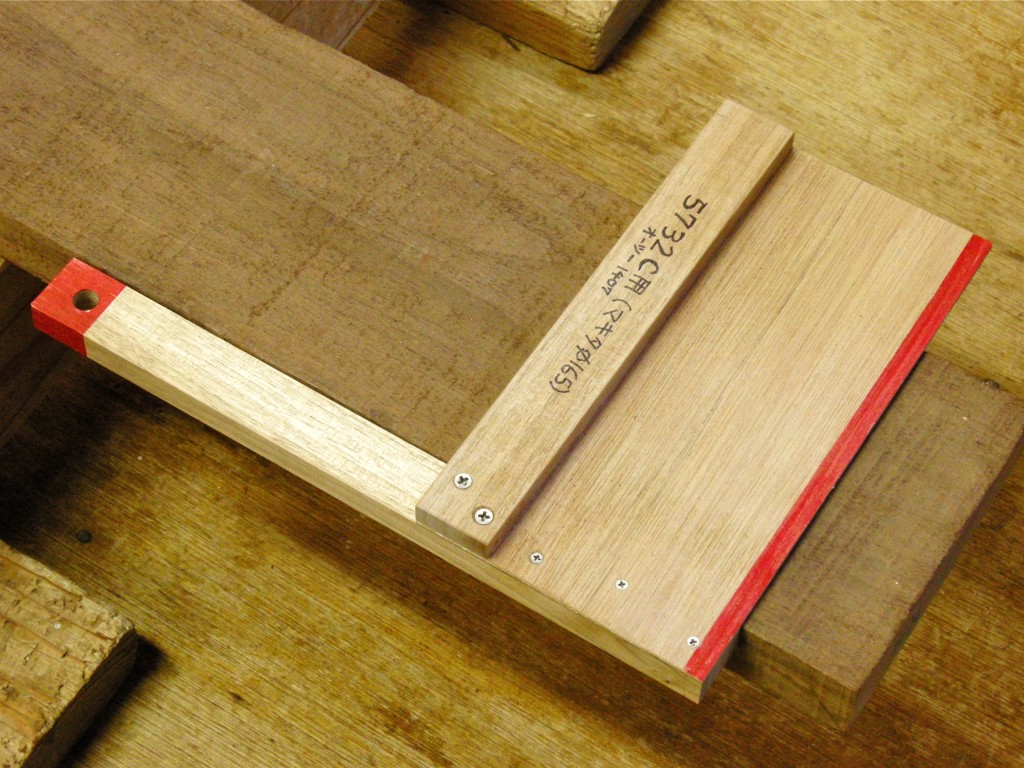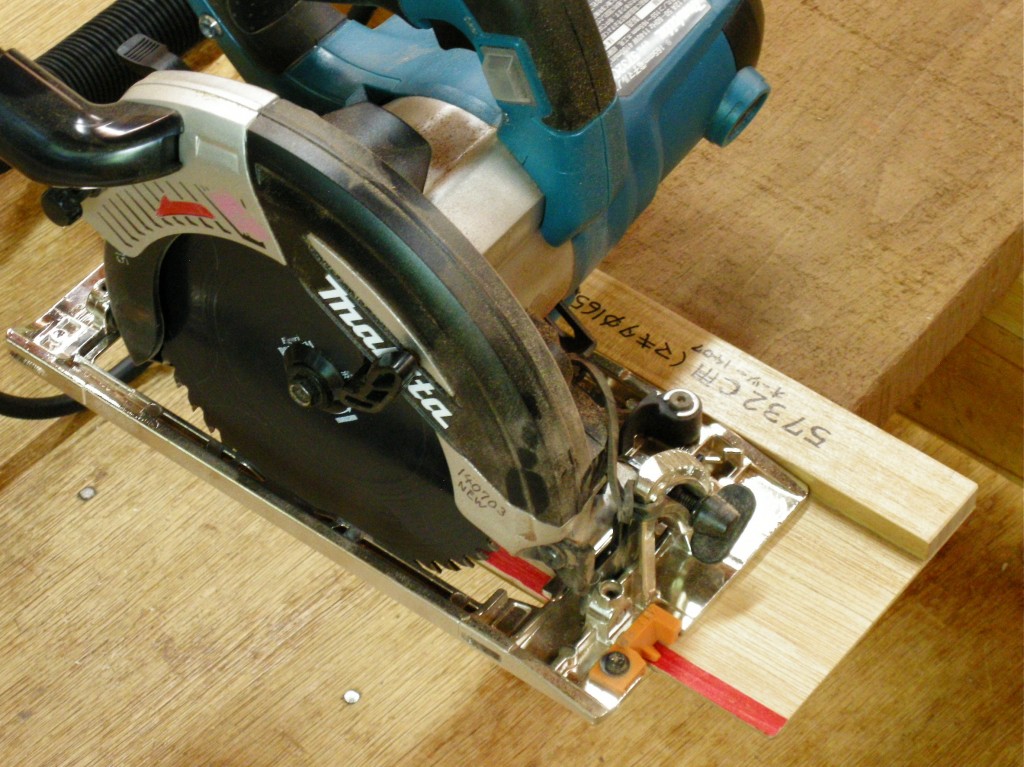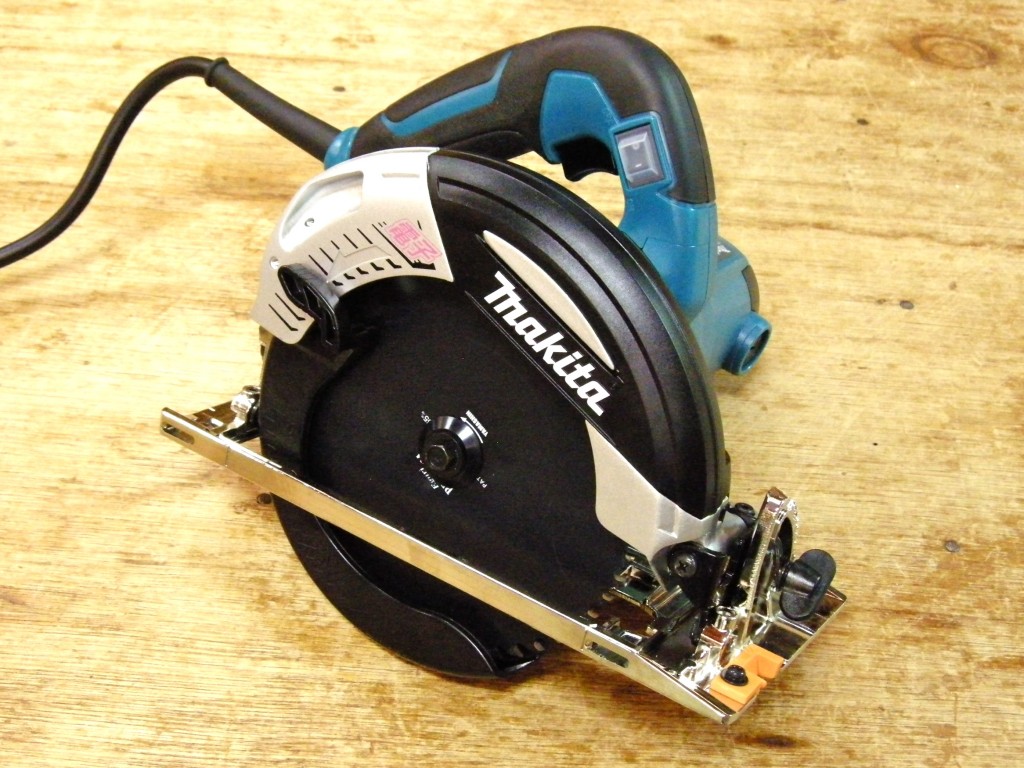短詩形同人誌『シテ』の同人を中心とする句会を、今年から隔月(奇数月第3水曜日)で行っていますが、今回はその3回目です。出席者は相蘇清太郎・今井富世・大江進・大場昭子・加藤明子・金井ハル・高瀬靖・西方ジョウ、南悠一・渡部きよ子の合わせて10名。(敬称略)
事前に無記名で2句投句し、清記された2枚の句群から参加者それぞれが当日2句づつ選び、合評が終わってから作者名が明かされるのはいつもの通り。まあいわばぶっつけ本番で、時間的にもすべてを2時間半のなかで行うので、かなり真剣に向かわないといけません。その緊張感も得がたいものです。では第一幕から。頭の数字は得点です。
2 吊り橋に弾みをつける青嵐
1 一族郎党ひきつれ浮いてこい
3 焼き鮎に鼻だけさめる眠り猫
2 若楓風吹き抜けし夕餉かな
1 コロッセオに猫一匹 殺すなネロよ
3 さみしくて水饅頭の餡の色
1 つばめの仔羽づくろいのみ覚えて旅立たず
1 葉のしずく風が拭いて夏至の月
0 ブラジャー剝いで水ナス齧る夏の白
2 朝顔やぐるりと家を絡めとり
得点がいちばん多かったのは3句目と6句目です。はじめの<焼き鮎に〜>は、猫はその語源ともいわれるようにしょっちゅう寝ていますが、鮎を焼いているとそれに反応してか鼻だけぴくぴく動かしているといった図です。わが家にも猫がいるのでよくわかる句ですが、「だけ」は言わずもながですし不要でしょう。五七五の短いなかに「鼻」をとり入れた時点ですでに鼻を特別視しているわけですから。作者は今井富世さん。
次の3点句<さみしくて〜>は私も取りました。俳句では悲しいとかうれしいとか寂しいといった感情を直裁に出すのはよくない、芸がないと一般的にいわれるのですが、この場合は水饅頭のあの半透明の葛を通してみえる餡の微妙な色合いが「さみしい」という感情とうまく呼応しています。たしかにそんな感じで、悲しいとか嬉しいというような感じではないですね。もっとも上五でいちど軽く切れるので、水饅頭の餡の色合いとさみしさとは直接的には関係なしと解釈することもできます。先に別の理由でさみしいことがあって、その気分のところにたまたま水饅頭と出会ったというふうにも。作者は南悠一さん。
2点句は3つありました。1句目<吊り橋に〜>は青嵐に吹かれて吊橋がいつもより大きく揺れている様子です。ただ「弾みをつける」では作為的かつ常套的なので、どんなふうに揺れているのかを客観的に具体的に描写したいところです。作者は大場昭子さん。
4句目<若楓〜>は、人家の玄関先とか庭先などによく植えられているカエデの樹の、まだわかわかしい緑の色と、そこを吹き抜けてゆく風のさわやかで涼しげな感じが目に浮かびます。じつは清記にはじめ「風」の字が抜けていたので、私は吹き抜けていったのが何なのかよくわからず悩みました。風とわかってみれば納得ですが、逆に優等生すぎてすこしもの足りない気も。作者は渡部きよ子さん。
次の10句目<朝顔や〜>は、通常好日的に表現されることの多いアサガオが、まるで蔦や葎類のようなちょっとおどろおどろしたふうに詠まれているのがおもしろいです。家のまわりをぐるりというくらいですから、半ば空家と化した住宅なのかもしれません。アサガオもそれくらい放置されるとイメージが変わるでしょうね。この句は私も取りましたが、欲をいえば下五の「絡めとる」をその語句を使わないでその感じをじわじわと出せればなおいいかなとも思いました。作者は西方ジョウさんですが、仕事の都合で出句のみの参加となりました。
1点句は四つ。<一族郎党〜>は私の句ですが、「浮いてこい」のフレーズそのものが夏の季語であり浮人形のことであるという予備知識がないと理解がむずかしいと思いますね。浮人形はお風呂などで遊ぶ玩具ですが、もちろんここでは大人が水底に沈んだ戦死者や入水者の悲哀や無念または呪詛を思い浮かべているところです。
<コロッセオに〜>はよく読むと下のほうと韻を踏んでいます。ありていに言えば語呂合わせにすぎないので、こういった句を今的で新しいとする見方には私は同意しません。コロッセオは古代の円形闘技場で、ネロはもちろん皇帝ネロで暴虐のかぎりを尽くしたことで知られています。作者は相蘇清太郎さん。
<つばめの仔〜>は中句で「のみ」とすでに詠んでいるので、最後の「旅立たず」は不要でしょう。作者は高瀬靖さん。<葉のしずく〜>は夏至の月が照る前に一雨でもきたのでしょうか。風がそれを乾かしているところでしょうが、それを「拭いて」とするのはどうかなあ。先の1句目の「弾みをつける」と同様に擬人的であり作為的すぎませんか。作者は加藤明子さん。
・・・・・
さてここまでで約1時間20分くらい経過しました。ひと休憩をはさんでから第二幕です。
4 今日一日合点ゆきたる合歓の花
2 幼いのだ尾を捨てられぬ青蛙
1 糠の中きゅうりなす指かくれんぼ
2 梅雨晴れの蝶高くたかく人逝けり
1 天の川どうか今宵は浅くなれ
2 息をつめ綿毛飛び越す小さき足
3 青嵐あの日の嘘が濡れてをり
1 キャベツにも小さな目玉の蝶止まりたり
2 蝉の穴極暑の棒の曲がり入る
0 校庭に水撒く部員の汗ひかる
最高点は1句目で4点<今日一日〜>の句です。読みは「きょうひとひ がてんゆきたる ねむのはな」ですが、その調べ自体がや懐古調でもあり、合歓の花のあの雰囲気とはよく響き合っているようです。いやがおうにも芭蕉の<象潟や雨が西施にねぶの花>を思い出すからかもしれませんが。作者は渡部きよ子さん。
次点3点句の<青嵐〜>は私には時勢が分かりにくかったです。夏の嵐がおそっているのは現在のことでしょうから、昔日の嘘を思い起こしてそれが濡れているということでしょうか? 嘘が濡れるということの意味はなんでしょう。青嵐とその嘘とになにか関連があるのかもしれませんが、よくわからないですね。よくわからないけれども妙に惹かれる句というのはあるわけで、この句もそうかも、です。作者は南悠一さん。
2点句は4句あります。2句目の<幼いのだ〜>は四肢が生えてもしばらくは尾が残っている蛙のようすですが、ここではむろん寓話的な表現です。「尻が青い」「尻尾をつけたまま」は未熟な者に対する皮肉の言葉ですが、この句では自分に向けての自虐的フレーズですかね。「幼くて」ではなく「幼いのだ」と強く言い切ったところに味わいがあります。作者は西方ジョウさん。
4句目<梅雨晴れの〜>は私も取りました。死者の魂が天空にのぼっていくことを蝶の姿に仮託しており、美しい追悼句です。「梅雨晴れ」という言葉も「高くたかく」というリフレーンも効いています。作者は高瀬靖さん。
6句目<息をつめ〜>は、タンポポかなにかの綿帽子を子どもが、その綿毛を壊さないように慎重に飛び越そうとしている図です。この句では「小さき足」が肝でしょうから、説明的に下五にそれをもってくるよりも上五に据えてまずそこに焦点をあてたほうがいいと私は思います。作者は加藤明子さん。
9句目の<蝉の穴〜>は私の句です。蝉は長い年月を地中ですごしたのち、土を穿って地表に出てくるわけですが、羽化を控えた日の夜に無事に地表に出られるようにあらかじめ穴を掘り終えているのではないでしょうか。蝉の羽化するころはとても暑い季節ですから、その蝉の穴にすらも熱気が侵入します。空気は陽気のいいときにはその存在をほとんど気にかけることもありませんが、極暑や極寒のおりはまるで固体のようなたしかな存在感を覚えます。高浜虚子に<去年今年貫く棒のごときもの>という有名な句がありますが、それも同様の感覚でしょうね。
1点句のうちの8句目<キャベツにも〜>は私が取ったのですが、キャベツと小さな蝶の取り合わせが新鮮です。私はこの蝶をジャノメチョウ(蛇の目蝶)もしくは翅裏に黒点のあるシジミチョウと受けとりました。モンシロチョウなどでは相方がアブラナ科のキャベツではあまりにも当たり前すぎるでしょうから。ただ「も」はなくてもいいかなと感じます。作者は相蘇清太郎さん。
・・・・・
さて、シテ7月句会はこれで終了しましたが、「おおむね当季の季語を入れる」という以外はいっさい制約のない投句をもとにした句会ですから、毎回どんな句がとびだすか非常に楽しみです。反面、選句はとても悩みます。よくできた優等生的な句をむろん評価しないわけではありませんが、個人的にはむしろ未完成でもいわゆる「問題句」をできるだけピックアップしようと考えています。視点や表現にオリジナリティがあるかどうかが大事で、他者にも問題提起となり刺激となるような句がのぞましいと思っています。
ただいわゆる形式的あるいは題材的な新規さはとくに私は求めてはいません。形やモチーフが従前の句にはない特異ものであっても、それだけで新しい句や詩になるわけではありません。インターネットなどで散見できる比較的年齢の若い方の「新しい句」のどこが新しいのか、私にはぜんぜん理解できないことのほうが多いです。現代用語辞典ではありませんが、ごく新入りの現代用語を用いてはいても、その切り口はあいかわらず陳腐で常套的で、なにやら珍奇な表現も必然性をすこしも感じません。
しかしながら世界は変転変貌し、100年前はおろか10年前には存在しなかったモノや現象や知見がいま身のまわりにも世界にもあふれかえっています。今を生きる人間の一人としては、それらのせっかくの「新しい」ことどもにも目を向けていかないと「もったいない」とは考えています。古来からの花鳥風月や伝統的風習文化を詠むだけが俳句ではないのもまたたしかです。