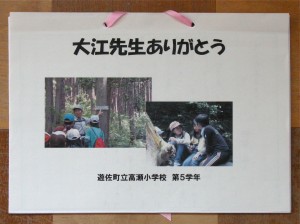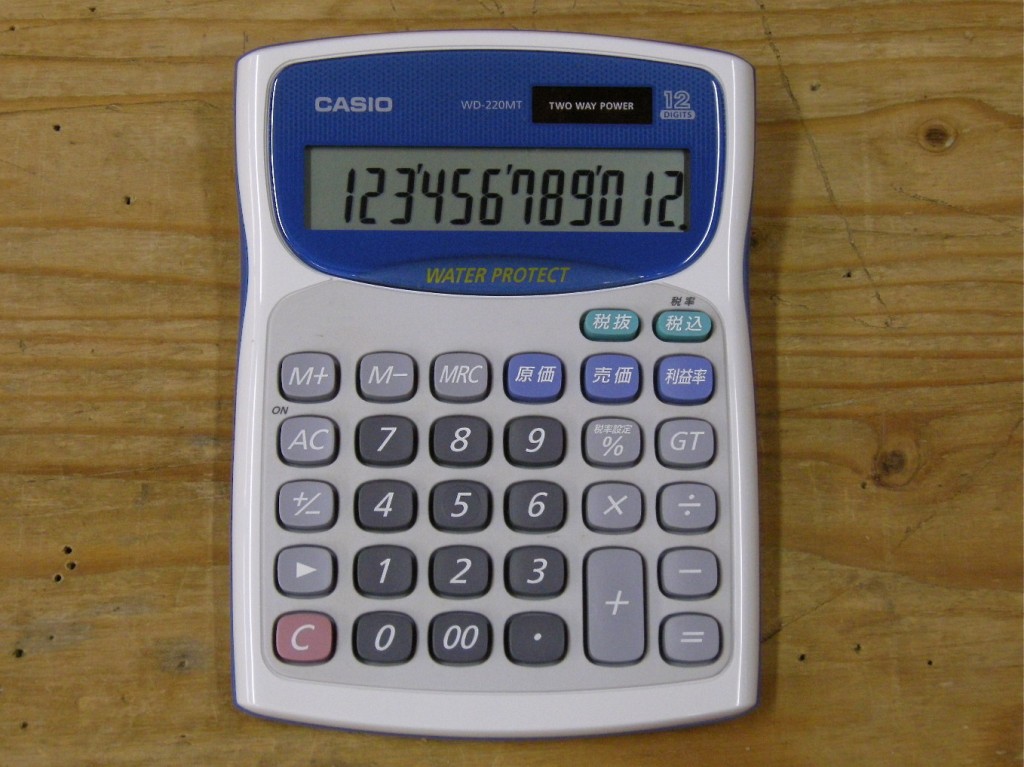いわずと知れたアップル社のスマートフォン、 iPhone です。ただし私が使用しているのは日本で発売された最初期の型で、 iPhone としては第2世代にあたる3G というモデル。もう2年半近く使っています。
いわずと知れたアップル社のスマートフォン、 iPhone です。ただし私が使用しているのは日本で発売された最初期の型で、 iPhone としては第2世代にあたる3G というモデル。もう2年半近く使っています。
その後、モデルは3GS、4 となり、私のはすでに旧型になってしまい性能的に不満も出てきましたが、今秋に発売が予定されているらしい iPhone 5が出るまで我慢するつもりです。とはいえ現在の3G でも愛用していることにはちがいがありません。実際に iPhone を使われている方にはいまさら説明するまでもありませんが、いちおうどういった機器なのか、他の携帯電話とどう違うのかを、以下簡単に記述してみたいと思います。
これは基本的に「いろいろなことができる携帯電話」ではなく「電話もできる超小型コンピューター」ととらえたほうが正解だと思います。そして操作のほとんどを液晶画面で行います。画面上のアイコンやボタンやキーボードなどを直接指で触れることによって入力・操作するわけです。銀行などにあるATMみたいなものですが、タッチするだけでなく、はじいたり(フリック)、軽くたたいたり(タップ)、つまんだり押し広げたり(ピンチ)といった動作と組み合わせるという、簡単かつとてもユニークな操作でこの超小型コンピューターは動きます。今ではこの「マルチタッチスクリーンパネル」で操作する方式の携帯電話が各社から出ていますが、2007年1月に最初の iPhone が米国で発売されたときはたいへんな驚きをもって迎えられたようです。
液晶ディスプレーは3.5インチあるので、本体の幅は62mmと通常の携帯電話に比べ大きめです。縦寸法は116mmで重さも133gとずっしり感があります。軽く小さい携帯電話に慣れた人にはこの iPhone 3G は重く大きく感じるかもしれませんね。私は手も大きいし「機能が凝縮されている」感じがあってぜんぜん気にはなりませんが。
電話をかけたり受けたりするのは若干めんどうかも、です。ふつうのコンピューターと同様、メインスイッチを入れても最初のホーム画面が出てくるまで30秒くらいかかります。通常は待受状態にしていますから、ボタンひとつで瞬時に初期画面が出ますが、それでも電話のアイコンを選択してからでないと電話をかけることはできません。かかってきた電話の保存や転送などといった機能は、そもそもあまり電話をしない私はいまだにちょっとまごついています。このあたりも「電話は iPhone の多々ある機能のひとつでしかない」というアップルの方針がみてとれます。
私が重宝しているのは写真関連の機能です。搭載のカメラは200万画素とあまり高くありませんしモード設定や絞り・シャッタースピードの選択もできない、いわゆるバカチョンです。が、バカチョンとしてはとても優秀で、どんな状況でもそれなりに写真が撮れてしまいます。私が持っているコンパクトデジカメではぜんぜん写せないよう場合でも、 iPhone ならなんとか写せてしまう。もちろん画像はかなり荒めで、「作品」を撮るには不向きでしょう(3GS や 4 では機能が格段にアップしています。ビデオ撮影もできます)。
現在私の iPhone には他のカメラで撮った写真も含め750枚が収納されています。工房の製品の写真と、自然関係の写真が大部分ですが、とくに自作の家具や木製小物の写真は簡易なカタログがわりにも使えます。初対面の方には自分がどういう仕事をしているかの強力なアッピールになりますし、写真の拡大も指先ひとつで簡単にできるので、細部のつくりも確認可能。むろん正式な仕事の打ち合わせにはA4サイズに精細プリントした資料を持っていきますが、それの前段階としては iPhone での画像は充分役に立ちます。
音楽は手持ちのCDをパソコンに入れたものから適宜 iPhone にダウンロードさせていますが、現在980曲収録。音質としては iPod と同様なので、イヤホンをさして聴くぶんにはけっこういい音だと思います。ただし私は他の仕事や作業や運動をしながら「ながらで」音楽を聴くことはまずないので、メモリ(128MB)を大幅にくっているわりには出番は少ないです。
他の機能としては、標準であらかじめ入っているアプリケーションソフトしかありませんが、住所録、カレンダー、メモ、ボイスメモ、計算機、時計、GPS、サファリ(インターネット閲覧ソフト)等があります。私がよく使っているのはカレンダーや時計の機能ですが、インターネットはパソコンにくらべるとあまりにも開示速度が遅すぎてむしろストレスを感じるので、出先でやむをえずという事情がないかぎり開くことはありません。このへんも3GS や 4 ではかなり改善されているようですが。
iPhone は日本では基本的にソフトバンクでしか扱っていませんし、契約も2年しばりで、他の携帯電話と違って通話だけでなく必ずデータ送受信=パケット通信も含む契約しか iPhone にはありませんので、通話基本料+留守電などのオプション+パケットしほうだいで月に最低6000円はかかります。携帯での電話は私は少ないので、多い月でも7000円程度ですが。携帯電話の料金と思えばずいぶん高いですが、超小型モバイルコンピューターだと思えば、まあ妥当かな。
さて iPhone のいろいろな機能について述べましたが、私がそれまでのごく普通のドコモの携帯電話から iPhone に切り替えた最も大きな理由は、じつはデザインです。機能云々はほんとは後付けのいい訳みたいなもの。 iPhone のデザインとそれを産み出したアップルの思想はすばらしいと思います。今でこそそのコピー然としたスマートフォンが各社からたくさん出ていますが、 iPhone を超えるものはないと私は感じています。
 私は農業にはタッチしていませんが、月刊誌『現代農業』をときどき買うことがあります。特集などで自分の仕事や暮らしにも非常に役に立つ記事が載っていることがあるからです。
私は農業にはタッチしていませんが、月刊誌『現代農業』をときどき買うことがあります。特集などで自分の仕事や暮らしにも非常に役に立つ記事が載っていることがあるからです。