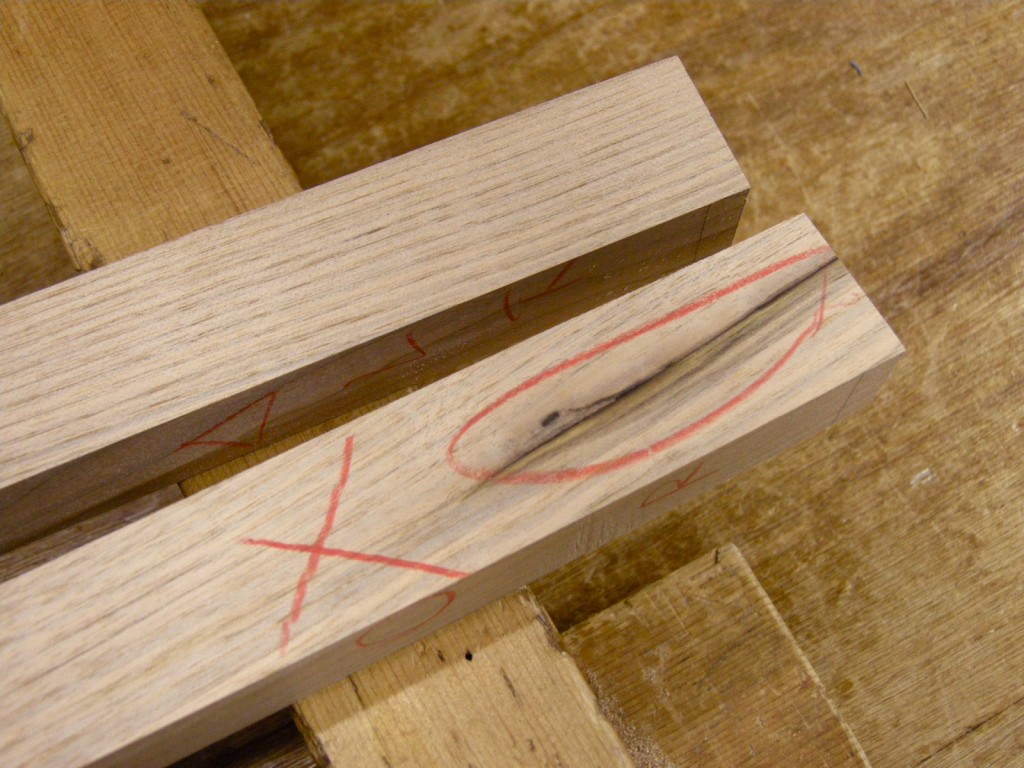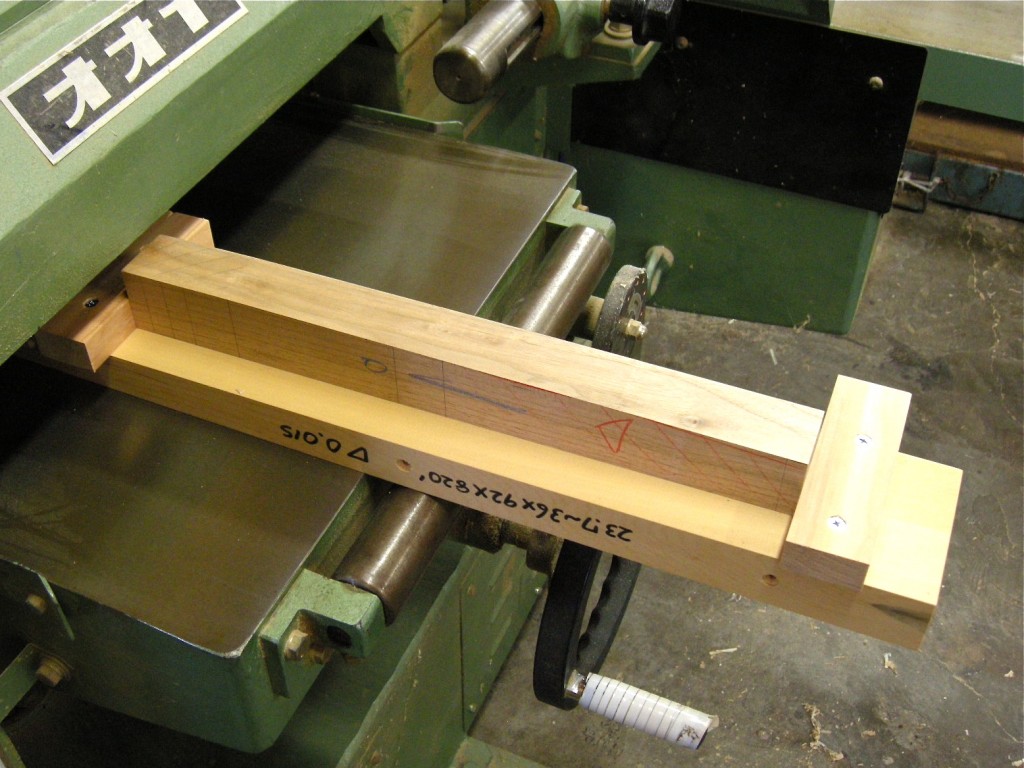9月27日に地元の遊佐高校の生徒25名、教師3名とともに鳥海山の標高1600mくらいまで登ってきました。南側斜面の滝ノ小屋〜河原宿〜心字雪渓というコースで、標高1100mの車道終点から標高差約500mの登行です。
「鳥海山の湧水」という科目で2000年から行っているフィールドワークの一環で、私が非常勤講師を務めています。これまでは麓や低山域の湧泉・湧水を観察していたのですが、その湧水の大元のひとつである膨大な積雪の痕跡である雪渓(小氷河)をいちど見てみようということになったものです。距離はたいしたことはないものの、道のようすや標高からいえばこれは明らかに登山というべきものなので、天気や生徒たちの行動を心配していたのですが、全員無事登って下ることができました。天気もよく、月山や葉山、丁山地や神室連峰など、遠くの山並みもきれいに見え、みな満足したようです。
河原宿の先の雪渓は、「心」の字の2画目にあたる大雪渓も今年はかなり後退して小さくなっていました。ほぼ毎年この時期、9月末から10月はじめにこの場所を訪れていますが、この十数年の間では今回が雪渓の規模がいちばん小さいように思います。おそらくこれも地球温暖化の影響のあらわれではないかと考えています。