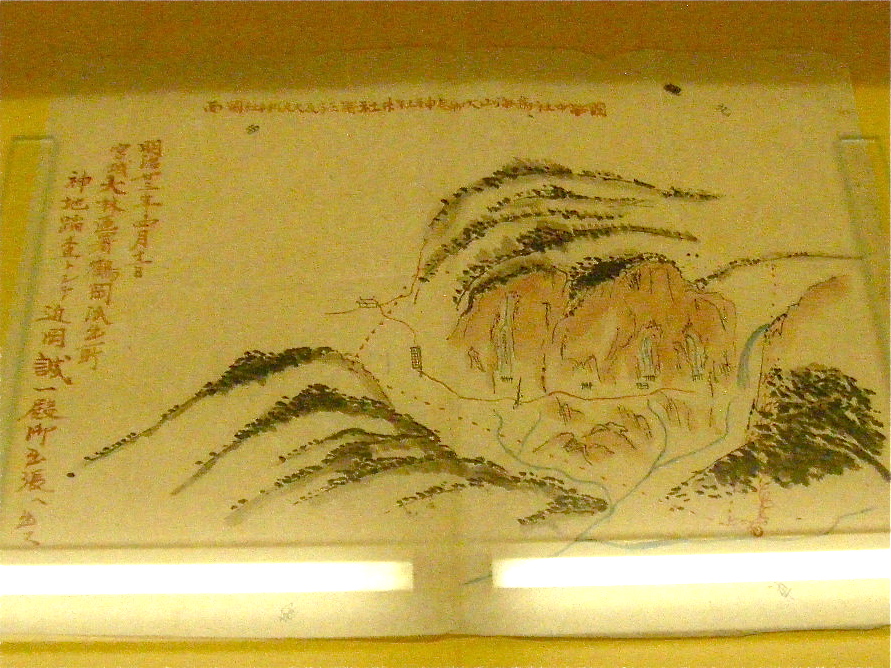湧水の温度などを計るのに私が使用しているのが写真のデジタル水温計です。株式会社佐藤計量器製作所(skSATO)のSK−250WPという機種で、防水型。測定の精度はプラスマイナス0.1℃です。サーミスタ式の温度センサーは1mのコードが付いているので、対象からややはなれている場合でも測定することができます。湧泉は足場がいいところばかりではありませんし、湧水の水面が岩間などからわずかにしかのぞいていないこともあるので、これは助かります。
湧水の温度などを計るのに私が使用しているのが写真のデジタル水温計です。株式会社佐藤計量器製作所(skSATO)のSK−250WPという機種で、防水型。測定の精度はプラスマイナス0.1℃です。サーミスタ式の温度センサーは1mのコードが付いているので、対象からややはなれている場合でも測定することができます。湧泉は足場がいいところばかりではありませんし、湧水の水面が岩間などからわずかにしかのぞいていないこともあるので、これは助かります。
電池は単三が四本ですが、本体右側の白い板はパワースイッチが誤って押されないようにするためや、液晶が割れたりしないようにするための自作の発泡アクリルの防護板です。以前、湧水の温度をいざ調べようとしたらスイッチが入りっぱなしになっていて電池切れだった苦い経験があるので、自分で取り付けたものです。
アクシデントといえば、こうした電子機器には故障がつきものです。まったくうんともすんともいわないのならダメだということがはっきり分かるのでまだいいのですが、測定・表示が微妙に狂った状態だと、それと気づかないまま正しいデータだと思って誤って記録してしまう可能性があります。そのため、ときおり他の温度計と比較したり、割れない限りは逆に信頼性がある0.1℃目盛の水銀温度計と比較したりする必要があります。
このデジタル水温計は価格22000円くらいのものですが、ホームセンターなどではこれより一桁安い値段で0.1℃まで温度表示されるデジタル水温計が売られています。しかしその値段の差にはむろん意味があるわけで、計測精度の差であり、機器の耐久性の差です。実際、鳥海山の湧水を調べ始めたごく初期の頃に、そのたぐいの簡易な温度計を使ったことがありますが、精度がわるく不安定なため、すぐに廃棄処分したことがあります。ちゃんとした電波時計でもないかぎり、秒針のある時計でも時・分はともかく、秒はほとんどあてにならないのと同様です。
※本機種は現在は廃番になっており、後継機種はSK-250WPIIです。あるいはひとつ上のモデル、SK-1260がいいかもしれません。