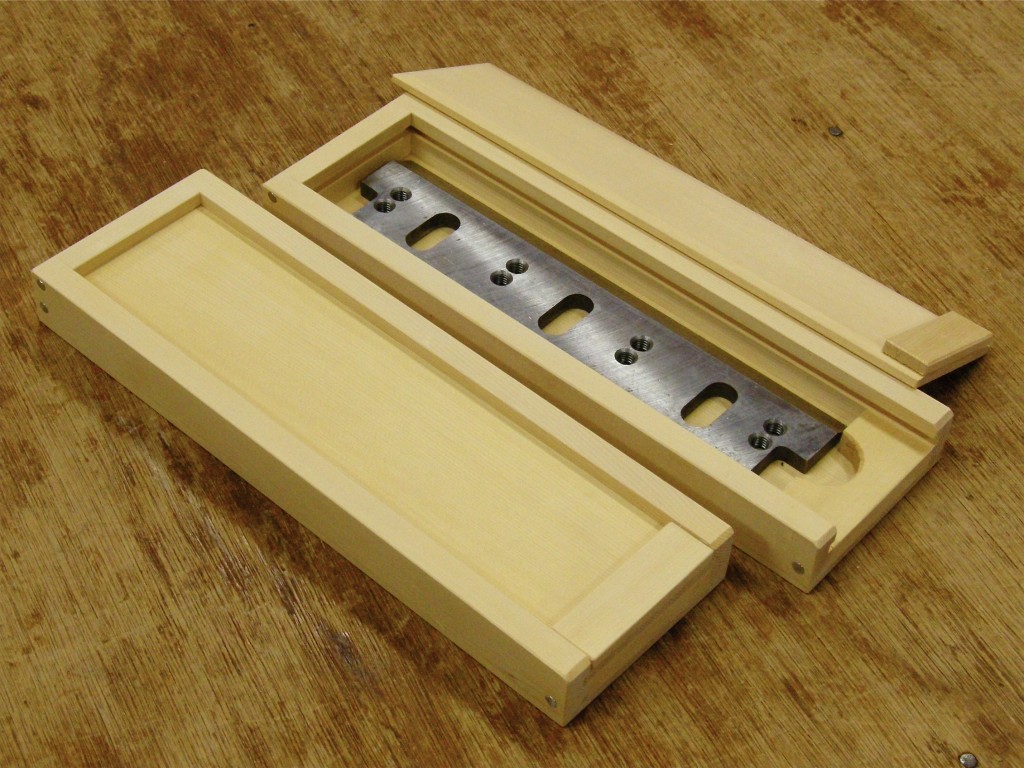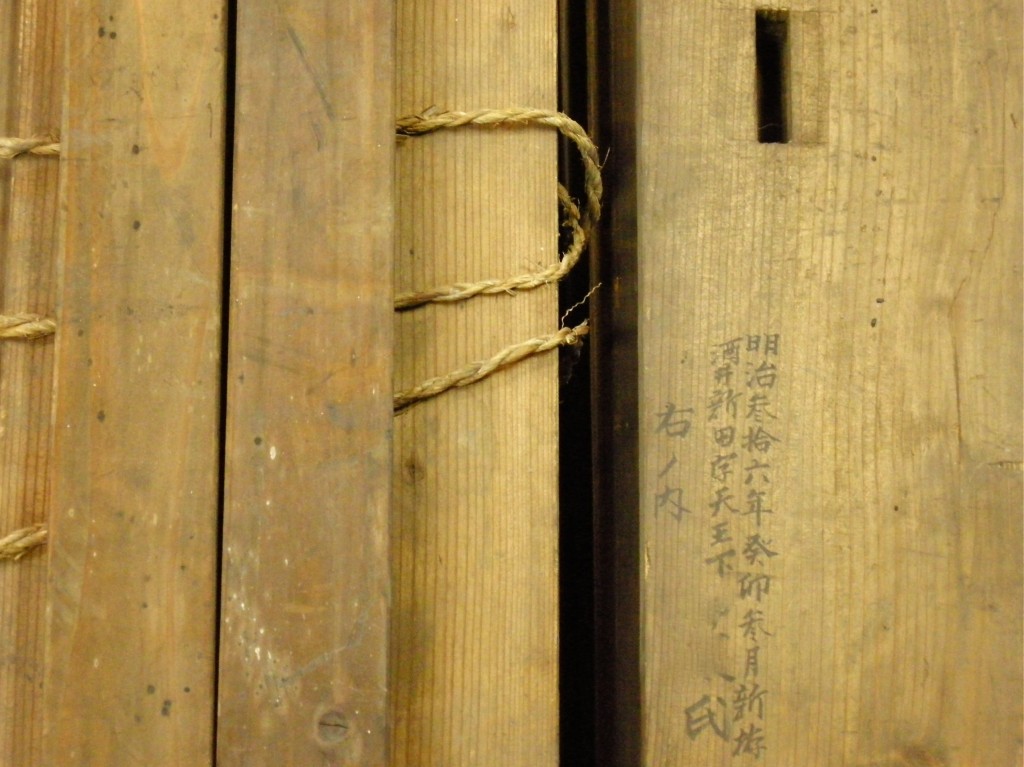奇数月の第三水曜日に開いているシテ句会の9月ぶんです。『シテ』は短詩形文学の発表と批評を目的とする同人誌で、年3回発行が目標ですがこれまで4号を発刊。メンバーは酒田市を中心に9名ですが、その中の活動の一環として句会もときどき行っています。今回の出席者は相蘇清太郎・阿蘇豊・今井富世・大江進・大場昭子・高瀬靖・南悠一・渡部きよ子の8名(敬称略)。
事前に無記名で2句投句し、清記された2枚の句群から参加者それぞれが当日2句ずつ選び、容赦のない自由な合評が終わってから作者名が明かされるのはいつもの通り。2時間半にわたる「バトル」です。では第一幕から。
2 秋夕焼飴煮る匂ひの港町
1 秋の陽はさびしさびしと傾きぬ
2 ひとり居に色なき風のレクイエム
0 詩はよせや巷に涙胸に雨
5 イナイ人ハ手ヲアゲテ八月十五日
0 恋ころぎ(虫に車)今宵逢瀬は茄子の陰
2 いわし雲被災地の泥深く重く
3 昼顔や道理に合わぬ雨がやみ
最高点は5番目の<イナイ人ハ〜>ですが、戦争で亡くなった人の無念さや悲哀がよく出ている、カタカナ表記が時代を感じさせよく効いている、という評価がある一方で、いかにも反戦というようで付き過ぎという意見も。こういった句はほかにはないのではないかという声もありましたが、まあ若干技巧的なにおいはあるかもしれません。ただひらがなではふざけすぎと取られかねないでしょうね。作者は私(大江進)です。
次点は3点句の8番目<昼顔や〜>です。「道理に合わぬ」をどう解釈するかですが、先の広島県などの集中豪雨とその甚大な被害をさしているそうです。昼顔は合っていて(朝顔ではだめです)、惨憺たる現場にぼうっと立ち尽くす被災者のようすがみえるようです。ただ理屈っぽい感じはあるので、道理に合わないという部分をもっと他の言葉で具体的に表せるといいと思います。作者は南悠一さん。
2点句は3句ありました。1番目の<秋夕焼〜>ですが、秋の夕焼け+飴を煮る匂い+港町で、材料がそろいすぎのきらいがあります。実景がそうだったということかもしれませんが、もっと焦点をしぼったほうがいいでしょうね。作者は大場昭子さん。3句目<ひとり居の〜>も上の句と同様に材料が盛りだくさんにすぎます。上・中・座と3つとも同じような感触の言葉が並んでいるので、逆におたがいに相殺してしまっています。作者は渡部きよ子さん。7句目の<いわし雲〜>は思いはよくわかるのですが、泥ですから「深く重く」とまで言ってしまっては常識的・常套的。言わずもがなという気がします。作者は高瀬靖さん。
2句目の<秋の陽は〜>は当たりまえすぎる情景ながらも駄目押しで「さびしさびしと傾きぬ」とまで言ったことで逆にすくわれた感があります。私はあえて採りました。作者は阿蘇豊さん。4句目<詩はよせや〜>は私にはまったくなんのことだかわかりませんでしたが、ベルレーヌの有名な詩をもじったものだそうです。そういえば「街に雨が降る、胸に涙が流るる」みたいな詩がありましたね。「詩はよせや」ということなので、そういう韻を多用し叙情にはしるのは止めろという意味のようですが、詩の素養がないと理解不能ですね。作者は相蘇清太郎さん。6句目<恋ころぎ〜>は他のいくつかの句とならんで材材が目一杯。事実がたとえそうだったとしても句にするときはもっと整理したいです。作者は今井富世さん。
ここまでで1時間20分ほど経過。今回は8名の参加とやや人数が少ないぶん、合評に熱が入りました。みなさん遠慮せずに「これはよくない。こうしたほうがいいのでは」と言い合いをするので、句会をたんなる趣味やお稽古事的にとらえている人には厳しいかもしれません。ほめられればたしかに誰しもうれしいのはたしかですが、忌憚のない批判こそは栄養、ありがたいことだと思います。
・・・・・・・
さて第二幕です。
2 白桔梗ゆれてためいき匂い立つ
3 銀漢の死にたる星もひきつれし
0 山肌を一切攫ひて秋立ちぬ
5 ものいはぬ女なりけり秋の水
1 枝豆の匂い立つ夕べかな
1 十薬の花の白きに怯えたり
1 はまなすの終日風に抱かれをり
3 落蝉に西風一つ眩しけり
最高点は4句目の<ものいはぬ〜>の5点。どうして女がだまりこんでいるのかなにやらわけがありそうですが、下五が秋の水とあるのであまり深刻な場面にならないですみました。秋の水ですから澄んだきれいな水で、女性の心もいまは落ち着いて冷静な感じにはなっているのでしょう。作者は高瀬靖さん。
3点句は2句あります。2番の<銀漢の〜>ですが、これは現代ならではの句。銀漢は銀河・天の川のことです。星にも生死があり、いま見えている星は何万年もはるか昔に発した光がいま地球に届いているだけであって、もしかしたらいまは消滅しているかもしれません。太陽系にいちばん近い恒星ですら4.3光年離れているそうですから。天文学の初歩的知識が広く共有されるような時代だからこそ、星空をみてそのような感慨がわくのであって、芭蕉の時代などにはけっして詠まれることのなかった句です。下五が「ひきつれし」なのでやはり上五は銀河や天の川ではなく銀漢でしょう。作者は私。
次の8番目の句<落蝉に〜>は光ではなく風がまぶしいというのがとてもいいですね。夏も終わりに近づき、風も北西からの風が多くなってきます。あるいは夕方になって、それまでの陸風が海風(日本海なので西風です)にかわるあたりでしょうか。佳句です。ただ表記としては<〜西風ひとつ眩しかり>としたほうがいいと思います。作者は今井富世さん。
次点2点句は1番目の<白桔梗〜>句ですが、ためいき+匂い立つ、とちょっと付き過ぎですしくどすぎます。どちらか削ってもっとさっぱりすっきりさせたほうが白桔梗の感じには合っているでしょうね。このままでは演歌みたいです。作者は阿蘇豊さん。
1点句は3句。最初の<枝豆の〜>は、たまたま1番目の句と同じ「匂い立つ」という言葉が使われていますが、通常それは良い香りがほのかにしかしたしかに漂ってくる場合に使われる表現だと思いますので、この句では適切ではないと思います。作者=相蘇清太郎さんによれば収穫する前の枝豆の匂いのことだそうですからなおさらですね。次の<十薬の〜>はドクダミのあの白い花のようすを詠んでいるのですが、個人的にはとても清楚なきれいな花(実際には総苞片)と思っているので、「怯えたり」はぴんときませんでした。ドクダミは名前が損しているのでしょうが、あまりいいイメージを持たれないことが多いのが残念です。作者は南悠一さん。
最後の<はまなす〜>はじつは漢字で書かれていたのですが、私のワープロソフトでは出てきません。すみません。ハマナスは海岸べりの乾いた土地に生えているバラ科の落葉低木で、花は野生のバラ科のなかでは大き目で紅色でとてもきれいですが、枝には鋭い刺がびっしり生えています。下五の「抱かれおり」がその点ですこしそぐわない気がします。過酷な土地に繁茂する強靭な植物ですから。作者は渡部きよ子さん。
3番目の句<山肌を〜>はやはり広島県などの先日の大水害を詠んだのだそうですが上句の山肌を一切攫うでは、読者には伝わりにくいでしょうしそれと立秋との結びつきがよくわかりません。甚大な災害があったにもかかわらず季節は関係なくめぐり、はやくも秋めいてきたよという一種の非情性を詠みたいのであれば、もっと表現を練らないといけないと思います。作者は大場昭子さん。
・・・・・・・
シテ句会は新しい体制になってこれで4回目ですが、句歴の長い私などの若干名をのぞくと他の方はほとんど初心者に近いといっていいと思います。詩はみなさんずっと長く書いてきているのですが、俳句となるとだいぶ勝手が違うようで、みなさん苦労されているようすです。とはいえさすがに詩作されてきているので慣れるのもはやいように感じます。つい自分の思いをいっぱい詰め込みすぎになりがちですけどね。
俳句は極度に短いということがくせ者でありまた魅力でもあります。発想の起点がなんであれ全部は五七五に詰め込めないので、どの言葉に光をあてどの言葉は捨てるのかというきびしい「引き算」が求められます。取捨選択し凝縮する。そのことが逆に詩的世界広げるという魔法のようなしかけです。