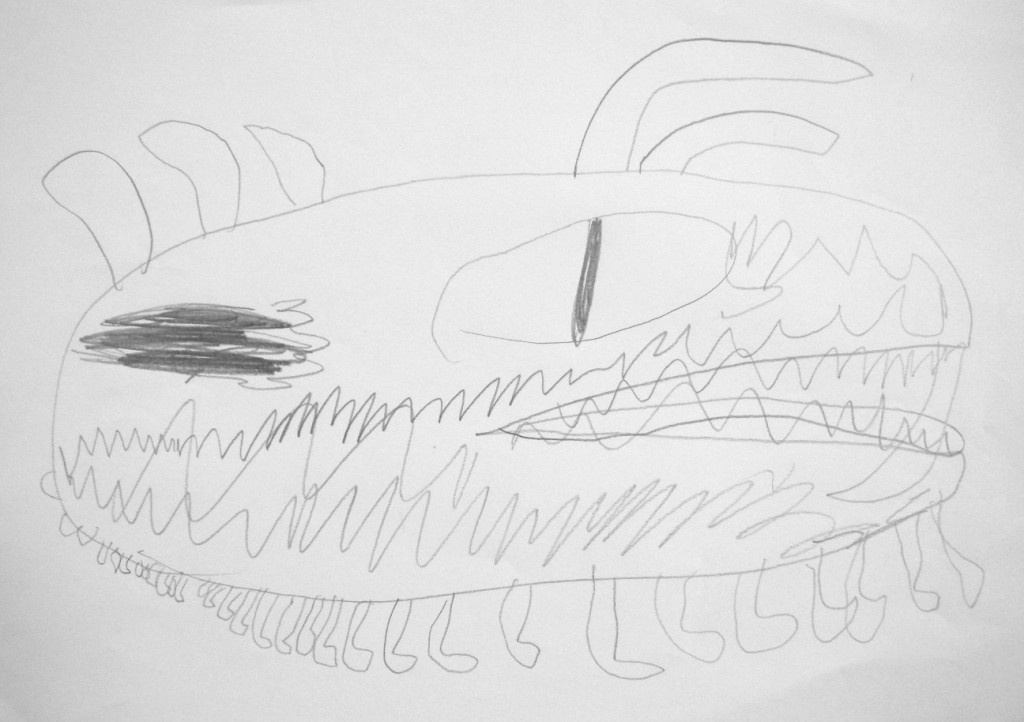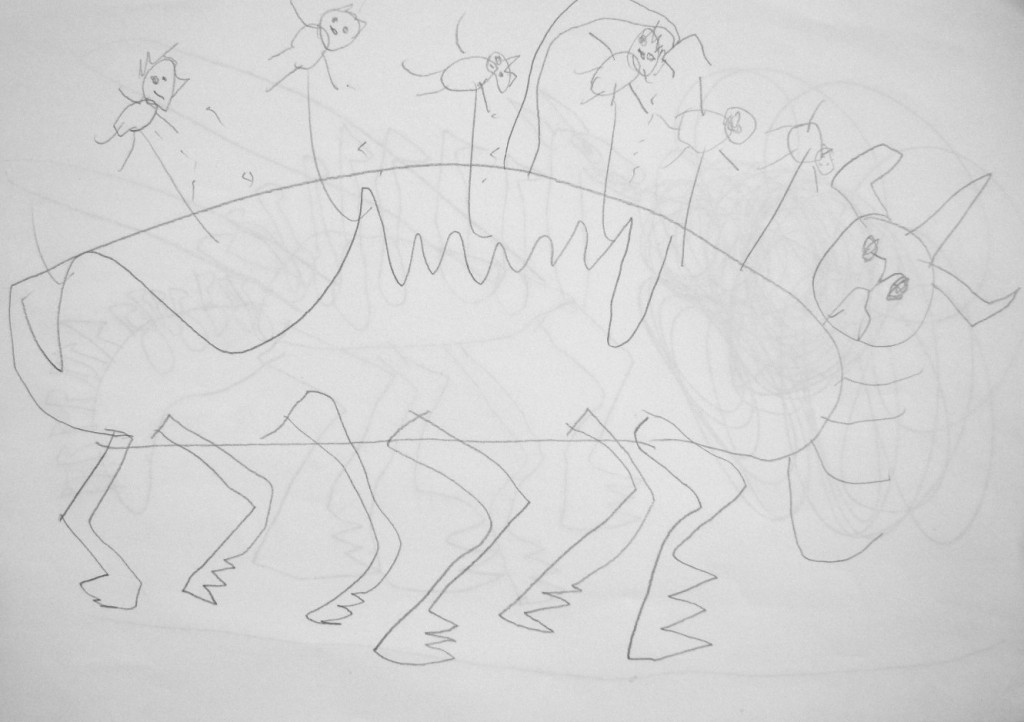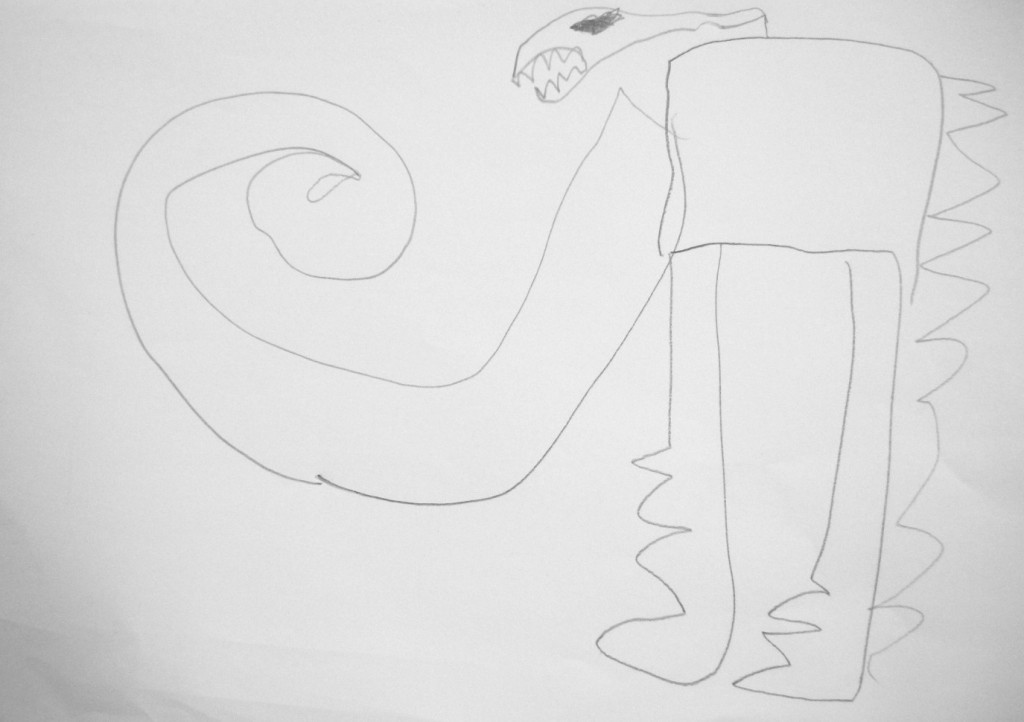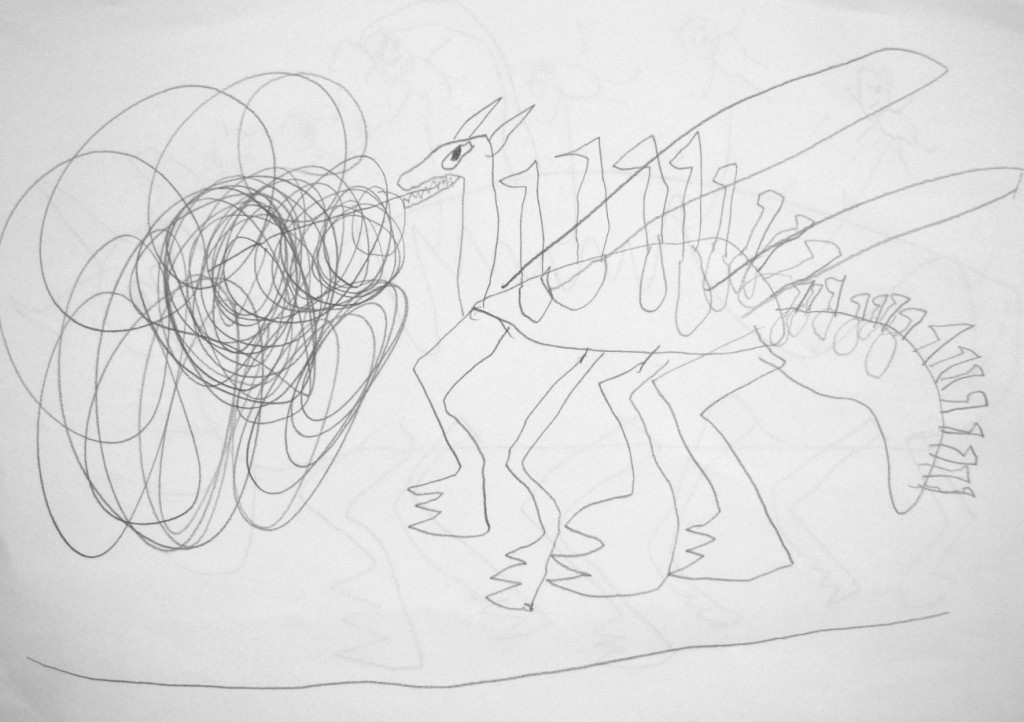11月25〜26日に岩手県大槌町および遠野市に行きました。大槌町は6月29日に次いで私は二度目の訪問ですが、今回はしらい自然館を拠点とする「鳥海山おもしろ自然塾推進協議会」の主催による、野菜類の販売とラーメンの炊き出し、民宿関連の研修視察が主な目的です。
一日目の25日の早朝5時半頃に、小型バス1台と1.5トンのパネルバン(箱形トラック)1台とに分乗して遊佐町を出発。総勢20名の参加ですが、秋田と岩手の県境をこえるあたりは降雪で、皆さん先行きをかなり心配しました。高速のパーキングや道の駅などで休憩をとりながら約6時間のドライブでしたが、さいわい目的地が近づくにつれ晴れ間がみえてきました。ラーメン炊き出し部隊は昼食に間に合わせなければならない関係で、前日にすでに現地入りして準備に追われているはずです。
海岸近くの釜石市や大槌町は、前回の訪問時よりは瓦礫等はだいぶ片付いているとはいえ、やはり惨憺たる光景であることには変わりがありません。今回はじめて震災被害地を目の当たりにした参加者も多く、やはりみな言葉を失っていました。テレビや新聞などで接するのと、自分の目で実際見るのとではまったく違います。
大槌町の仮設住宅は多数分散していますが、その中でもおよそ500世帯といういちばん大きな規模の「大槌第5」に向かいました。壊滅状態の海岸部の平地から大槌川に沿って上流に10km近くもさかのぼったところの、決して広いとはいえない所に仮設住宅がたくさん並んでいます。集会所のかたわらに野菜類をおろして野天販売を開始。
事前に今回の催事は役場を通じて伝えてあるので、すでにたくさんの方が並んでいます。大根やネギ、白菜、人参、ごぼう、ジャガイモ、水菜、パプリカ、ほうれん草、青菜、ちんげん菜、米、餅、笹巻きといった遊佐町産の食べものを廉価で販売する一方、集会所内ではラーメン約200食を無料で提供しました。両者ともたいへん盛況だったのですが、風がものすごく強いのにはまいりました。ときおり突風が襲ってきて、並べた野菜類もなにもかもが吹き飛ばされてしまいそうになるほどです。それに気温は3〜5度くらいでしょうか、寒いです。着込んで、トラックを風よけにしながらの約2時間あまりの販売でした。
夕刻からは場所を遠野市に移し、土渕町のたかむろ水光園という大きな旅館に泊まりました。大方は鉄筋コンクリートの新しい建物ですが、一部に南部曲り家が併設してあり、私も含め6名はこちらの大座敷・小座敷に泊まりです。本館からの長い渡り廊下や曲り家内部は各種の展示場も兼ねており、千本にもおよぶという囲炉裏の自在鉤や、鍋や釜や鉄瓶などの鋳物、それに遠野市の水道事業に使われた鋳鉄の水道管などがたくさん展示されており、圧巻です。
※ かんじんの仮設住宅や野菜等販売のようすは、カメラの不備で撮影できませんでした。すみません。二日目26日についてはまた明日にでもレポートします。