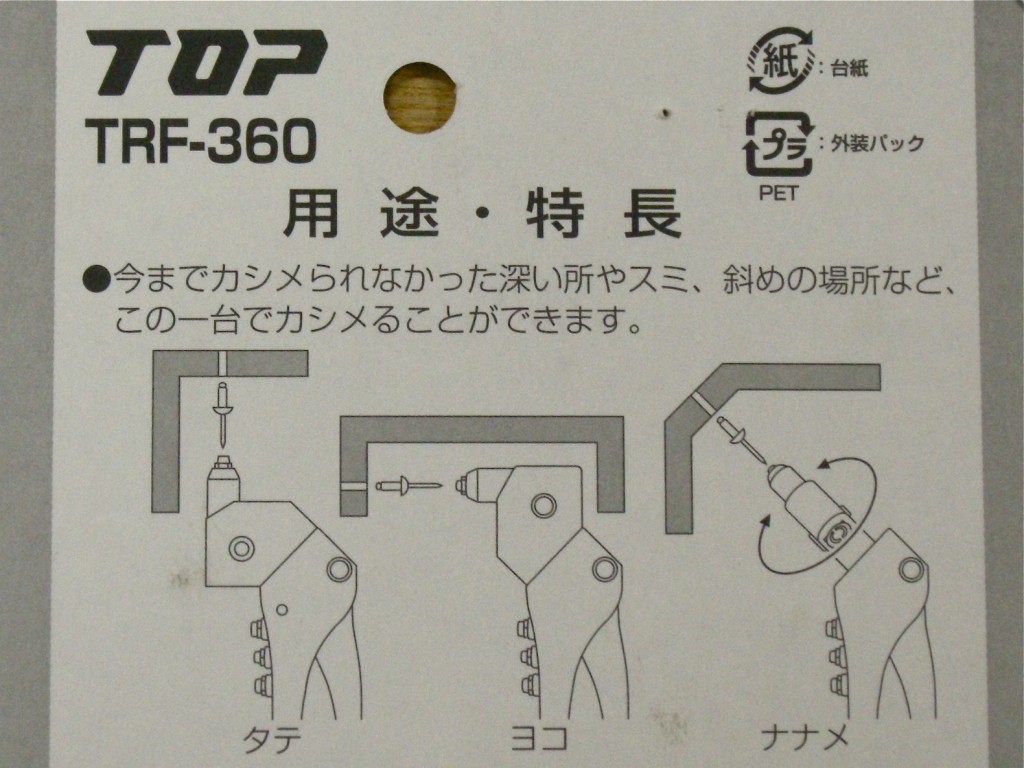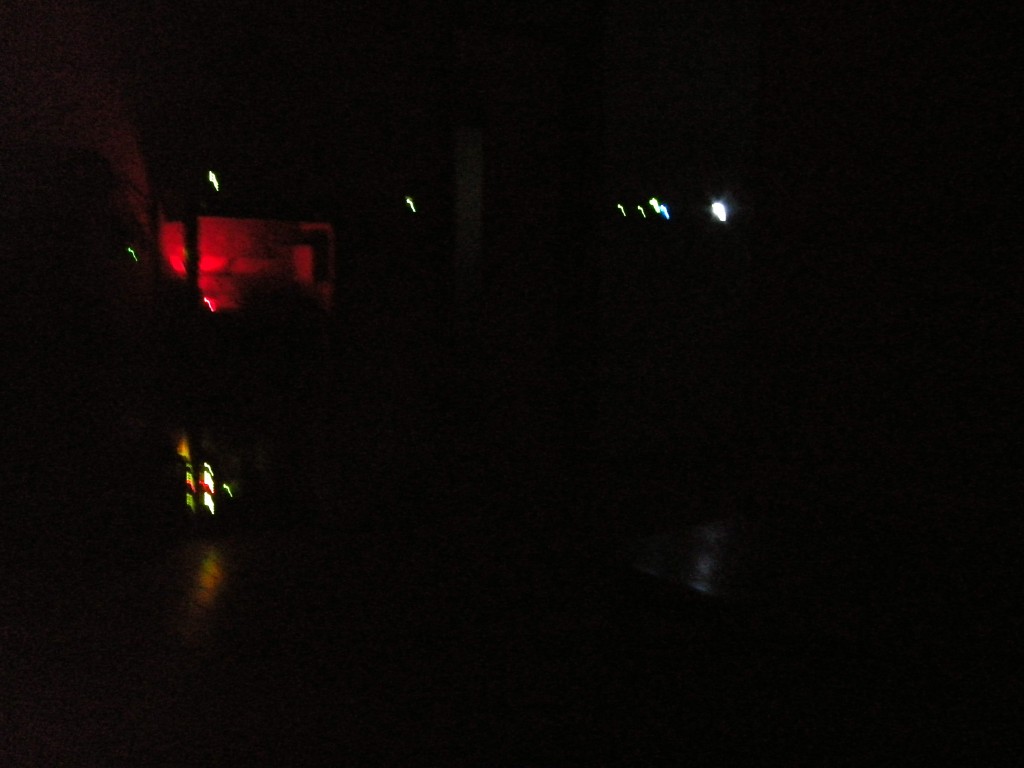さまざまな骨も散らばり貝寄風に
旧暦2月20頃に吹く季節風で、海辺の貝殻が吹きよせられるほど強いということで貝寄風(かいよせ)という。新暦では3月の終わり頃。こちらでは耳慣れない言葉だと思ったら、大阪四天王寺の精霊会の舞台に立てる筒花を、この風で吹きよせられた貝殻で作ったことにちなんだ名称とのこと。なるほどね。そういった宗教的行事は別に置いておくとしても(私自身はほとんど関心がない)、なかなかに味わいのある春の季語ではある。/ここ山形県庄内地方は日本海に面していることもあって、冬場の北西の季節風はたいそう強い。貝殻はもちろん砂も遠く吹き飛ばされて陸地に堆積する。1年に1mm平均積もったとしても千年で1m、一万年で10mである。実際高さ約50m、幅2〜3km、長さ35kmという日本最大級の砂丘(庄内砂丘)が鎮座しているほどである。まさに「塵も積もれば山となる」がものの例えではなく現実そのものであったわけだ。
啓蟄やお前が先に行けと言う
春になり暖かく陽気がよくなってくると、地中から爬虫類や両生類・昆虫など、虫偏の生き物たちがたくさん這い出してくる。しかしながらそれを待ちかまえ餌として食う生き物もいろいろいるわけで、啓蟄は「拝啓、◯◯様」とばかりはいかない、悲喜こもごもである。/戦闘であれ冒険や調査であれ、言うまでもないがいちばん先に立つ者がいちばん危ない。とくに大災害や戦争などであれば、まずは部下・手下を先に行かせて状況を探る。責任者や大将が出ていくのは状況が把握でき、とりあえずの「安全」が推定され確保されてからのことだ。映画やアニメみたいに大将がまず先頭を切って敵陣に乗り込むなんてことは絶対にありえない。
ひしめきて暗がりばかりや苗木市
4月から5月にかけて地元の祭りの日やその前後に苗木市が開かれることが多い。だいたい2〜3日程度の即売会なので、草木の苗や幼木などが沿道や公園の空き地などに所狭しと並ぶ。現在では大きめのホームセンターなどへ行けば年中売っているし買うことができるが、昔はそういう機会や場もそれほどなかったので、祭りに連なる縁日の苗木市は非常ににぎわったものだ。植物もいっぱいだが、人間もいっぱいでごったがえしていた。いくらかみな興奮状態にあるので、つい財布の口もゆるむというわけである。値段はものにもよるが、必ずしも通常の市販価格にくらべとくべつに安いということもないのだが、今買わないとなくなってしまう、他の人から買われてしまうという心理がはたらくからなのか、けっこう売れ行きもよかったのではないかと思われる。/私も父の影響もあってか子供の頃から植物は大好きで、苗木市にはよく連れていかれたし、中学・高校の頃は小遣いをためて一人でサボテンや多肉植物などを買いに行った。そして300円、500円くらいの買い物にさんざん迷うのであった。