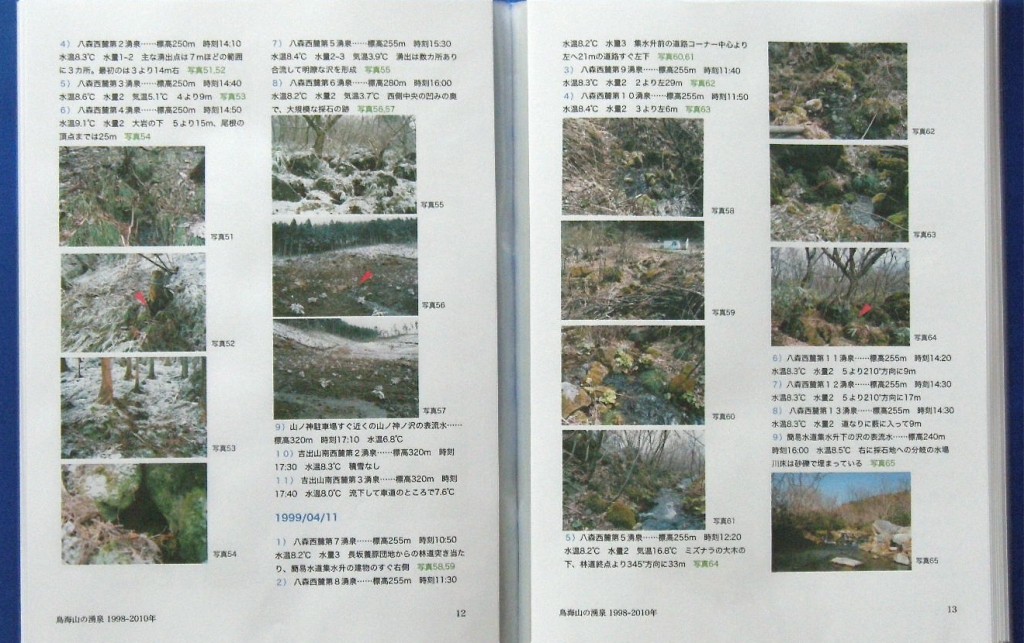Janatはジャンナッツと読むらしいです。フランスの紅茶です。たまたまですがブランドマークが向かい合った2匹の猫で、猫好きの私にはこんなちょっとした偶然がうれしっかたりします。
私は紅茶やコーヒーをよく飲みます。ただし紅茶はリーフティーに限りますし、コーヒーはドリップです。ティーバッグやインスタントコーヒーは基本的に敬遠。といってもそれほど銘柄や品質にこだわっているわけではなく、コーヒーなら100g当たり300~400円程度、紅茶も100g当たり600~1000円くらいのふつうのものです。もっとずっと高いコーヒーや紅茶を買って飲んだこともありますが、たしかによりおいしいのだけれども「全然違う!」というほどの大きな落差は私の舌では感じられませんでした。ふつうのものでも一杯当たり30~50円くらいになるし一日に何杯も飲むので、単価が何倍もするような高級なコーヒー・紅茶はちょっと無理があります。
さてJanatの紅茶ですが、とびきりというわけではないにしても充分おいしいです。値段も通販だと200g入缶で1000円しないので、非常にお買い得。あ、水だけは最近ウルサイです。胴腹ノ滝に飲料用の水を1週間から10日ごとくらいに汲みに行きますが、ここの超軟水でいれたコーヒーや紅茶はやはりいちだんとおいしく感じられます。