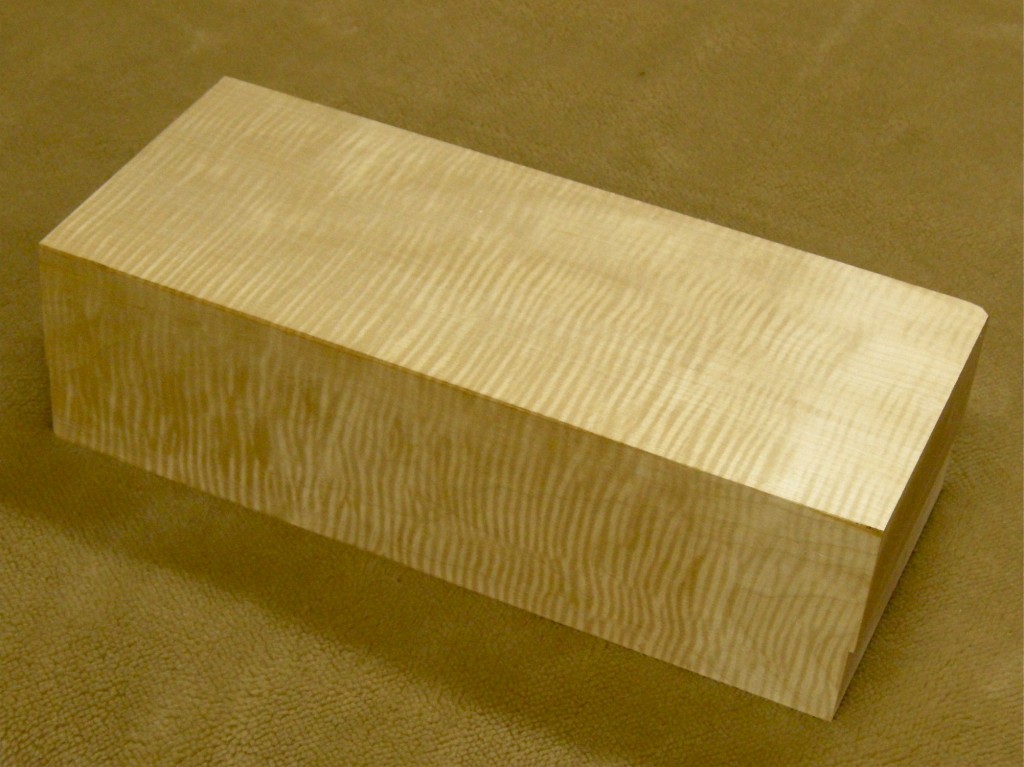ストーブの前でくつろぐ猫2匹。黒っぽいキジトラがミャースケ、下の大きいなんともいいがたい模様のがトントです。まるでミャースケが小さい若い娘で、トントが肝っ玉母さんみたいですが、ほんとうはミャースケのほうがずっと年上、というよりかなりの高齢。トントは猫としてはけっこう大柄だと思いますが(6キロくらいあるかな)、気はとてもやさしく、ミャースケから寄っかかられても、なにをされてもちっともいやがりません。
ストーブの前でくつろぐ猫2匹。黒っぽいキジトラがミャースケ、下の大きいなんともいいがたい模様のがトントです。まるでミャースケが小さい若い娘で、トントが肝っ玉母さんみたいですが、ほんとうはミャースケのほうがずっと年上、というよりかなりの高齢。トントは猫としてはけっこう大柄だと思いますが(6キロくらいあるかな)、気はとてもやさしく、ミャースケから寄っかかられても、なにをされてもちっともいやがりません。
猫は本来は単独行動する動物だと思いますが、寒くなると「そんなことはどうでもいいのだ」とばかり、よくくっついています。一匹でいるより各段に暖かいですからね。原理主義よりも現実主義。二匹とものどをごろごろ鳴らしながら極楽気分です、たぶん。