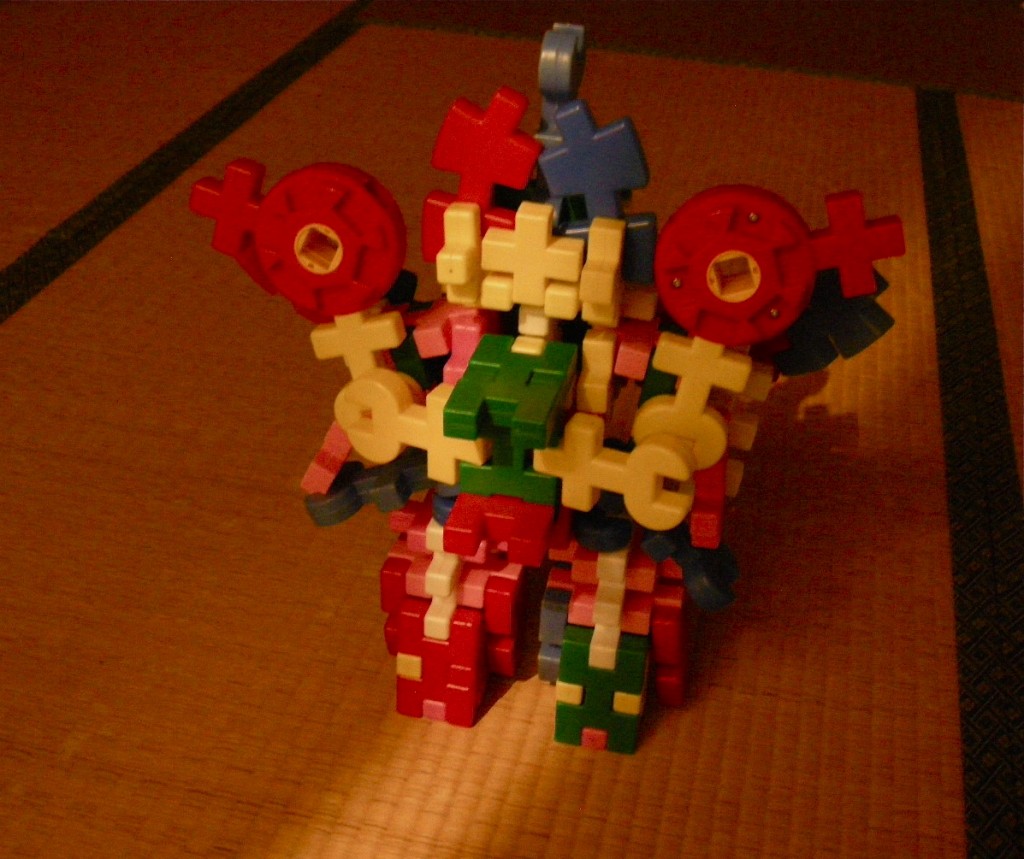10年以上も前に仕入れたオニグルミの板です。直径65cmほどの大きな丸太を指定の厚さで挽いてもらったのですが、厚さ30〜40mm強の板が十余枚取れました。薄い材や芯割れのある材はあらかた使ってしまいましたが、いちばん上等な板が4枚残っています。写真はそのうちの1枚です。
小さな節や入皮が若干ありますが、4枚ともほぼ無地にちかいAAグレードの板です。2枚矧ぎ合わせれば幅80cm長さ180cmくらいの甲板のテーブルや座卓などが2卓作れるでしょう。白太の変色もほとんどないので、その部分も使えば奥行60cm程度の一枚板のデスクもできそうです。

オニグルミ(以下クルミ)Juglans mandshurica subsp.sieboldiana はクルミ科クルミ属の落葉高木で樹高は最大25mほどにもなりますが、太さは胸高直径でせいぜい70〜80cm程度にしかなりません。つまり食卓のような対面使いのテーブルなどの一枚板として使用するにはちょっと幅が足りないわけです。仮に径70cmの丸太でも芯割れをよけ、変色・虫が付きやすい樹皮側の白太も含めないとすると、板幅としては50cmくらいが取れる寸法の最大ということになります。
クルミは日本と樺太に産しますが、日本では全国に分布し、主に山地の谷筋や川沿いなどに生えています。材木としては導管の目立たない散孔材で、絶乾比重は0.53前後と広葉樹としては中位ですが、そのわりに強度が高く粘りがあり狂いにくいのでほとんどすべての家具・木工品に適応します。硬さはケヤキやナラやカエデ等の他の広葉樹ほどには硬くなく、また色合いも写真のようにそれほど濃くも淡くもない、ミルクたっぷりの紅茶色といった感じです。
硬さや色艶がほどよく、丈夫で加工もしやすい。強く主張しすぎない、といった理由で私は個人的にもっとも気に入っている材料のひとつです。事実、当工房では広葉樹のなかではいちばん使用量が多い材料です。お客さんに説明するときも少なくとも名前くらいはすぐに通じますし。
これだけすぐれた材料なのに、巷の家具店などでクルミでできた家具・木工品をあまり見かけないのは、用材の産出量が少ないからです。樹種としては特別珍しいわけではありませんが、まとまって生えているとか群落を成していることはなく、山野にぽつんぽつんとまばらに生えている程度。人為的な育成もほとんどされていないので、流通経路にのるクルミ材はわずかですし、供給が非常に不安定です。これではとても大手の家具メーカーがメインの材料として採用するのは無理です。
しかしそれは裏をかえせば、当工房のような零細木工房にとってはひとつの魅力に転化しうるということでもあります。とくに特注品の場合は、どうせならふつうの家具屋さんなどでは売っていない材料で特別にあつらえることができるのも、いわゆる「手作り」の魅力であり訴求ポイントでしょうから。ただし今回ご紹介したような大径木からの通直な幅広材はきわめて品薄・貴重で、今後ますます入手が困難になると思います。