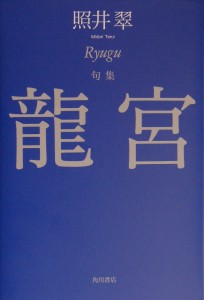
ずっと気にかかっていた句集ですが、やっとインターネットで手に入れました。照井翠(てるいみどり)さんの第五句集『龍宮』です。昭和37年生まれ、岩手県釜石市在住の方です。と、ここまで書けば題名の「龍宮」がなにをさすのかはもう明らかでしょう。4年半前の3月11日に東北地方太平洋沿岸を襲った大津波で、犠牲となった方々に捧げる鎮魂を主体とする句集です。
はじめはホチキス止めの私家版として出したものが、その内容に驚嘆・共感した周りの人たちのすすめで2013年7月に角川書店よりあらためて出版されたという経緯からも伺い知れるように、俳人はもとよりもの書きであればうちのめされるようなたいへんな句集です。
表紙は深い海の底を想わせる群青色。6章にわかれ計223句がおさめられていますが、1ページに1句だてというたいへんぜいたくな作りです(装丁は間村俊一)。ブログにはどの句を取り上げるか迷いに迷ってしまうのですが、以下35句を選んでみました(私のパソコンでは旧字で出てこないものがあります。ご容赦を)。
黒々と津波は翼広げけり
家どれも一艘の舟津波引く
泥の底繭のごとくに嬰と母
双子なら同じ死顔桃の花
御くるみのレースを剝げば泥の花
春の星こんなに人が死んだのか
毛布被り孤島となりて泣きにけり
剥製の鹿と人間泥の穴
朧夜の首が体を呼んでをり
朧夜の泥の封ぜし黒ピアノ
梅の香や遺骨なければ掬ふ泥
一列に五体投地の土葬かな
春昼の冷蔵庫より黒き汁
春光の影となるものなかりけり
唇を噛み切りて咲く椿かな
漂着の函を開けば春の星
北上川の青蘆の丈長き髪
ほととぎす最後は空があるお前
トンネルの奥の万緑閉ぢきらる
蝶の逝く摑みし巌に摑まれて
蟻しきりに顔掻き毟るなくならぬ
蟇千年待つよずつと待つよ
面つけて亡き人かへる薪能
流灯にいま生きている息入るる
夏の果波間埋むる白き羽根
水引のどこまでも手を伸ばしくる
穴という穴に人間石榴の実
鮭は目を啄まれつつ産みにけり
蜘蛛逝きぬ己の糸の揺り籠に
小鳥来るきのふは番ひけふは一羽
葉牡丹の大きな渦に巻き込まる
釜石は骨ばかりなり凧
三月や遺影は眼逸らさざる
何処までも葉脈の街鳥帰る
朝顔の遥かなものへ捲かんとす
大自然の猛威を目のあたりにして、作者は呆然と立ち尽くし、悲嘆にくれ、やがて氷が溶けるように「運命」を受容し、いくぶんかは平安をとりもどしてゆく。そんな時間と精神の推移がわかります。この大震災では少なからぬ文学作品=俳句や短歌・詩・小説などが著されましたが、この句集は当事者ならではの緊迫感があり、多くの読者や評論家が指摘するように他を圧し群を抜いていると思います。
ただあえて言うならば、大津波によって大勢の人が亡くなったそのむごたらしい光景に対して、無理からぬとはいえ事実をそのままに羅列するに終わっている句も散見されます。ドキュメンタリーであればそれでよくそれで正解でしょうが、俳句として表現するなら詩的跳躍がほしいところです。もちろん、3.11という比類なき災害に遭遇してさえも文学的昇華を期待するのは、文学者としての一種の業かもしれませんが。













