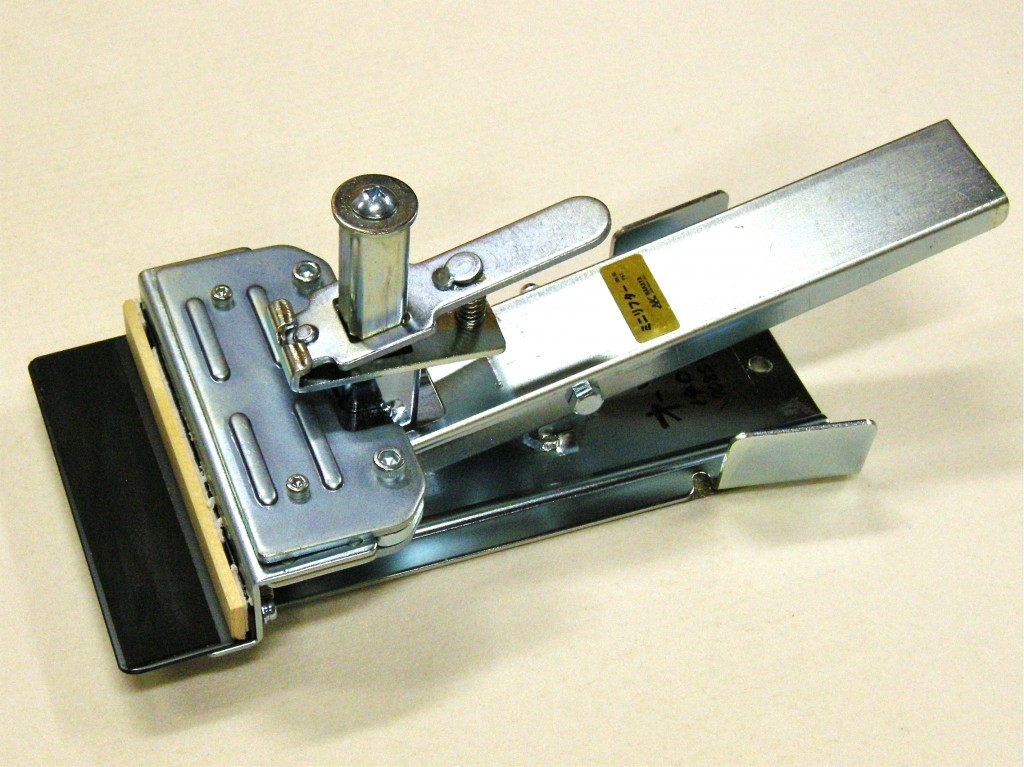工房の掃除をして帰ろうとしたら、コンクリートの上を長さ30cmくらいの小さなヘビが這っていました。すぐにほうきでちりとりがわりの「み」に追い込んで捕獲し、撮影しました。背景がオレンジ色なのは「み」がその色のプラスチックできているからですが、とっさの判断ながらつるつるすべってヘビも簡単には脱出できないのが幸いでした。
全体が緑味をおびた茶褐色で、模様らしい模様はありません。太さはいちばん太いところでも1cmあるかどうかくらい。なんという種類のヘビなのかすぐには分かりませんでしたが、少なくともマムシやヤマカガシという毒蛇ではないことはたしかなので、じっくりと10枚ほど写真を撮らせてもらいました。ヘビのほうは危険を察知しておびえているのかとぐろを巻いたまま、ほとんど動きません。指先でちょっと触ってみましたが冷たくさらっとした感じです。撮影が終わったので戸外の草むらに放してやりました。
自宅にもどってさっそく調べてみると、どうやらヒバカリ(日計・日量)というヘビのようです。ユウダ科ヒバカリ属で、日本に産する主なヘビ8種類のうちの一種(島嶼も含む全体では36種)。それほど珍しい種ではありませんが、地味な色合いや薄明薄暮型の活動のため目立ちません。私も明瞭に認識したのは今回がはじめてです。毒はなく全長40〜65cmほどと比較的小型のヘビです。上の写真でもわかりますが口吻から頸部にかけて白色または淡黄色の斑紋があり、これが識別のポイントでしょうか。