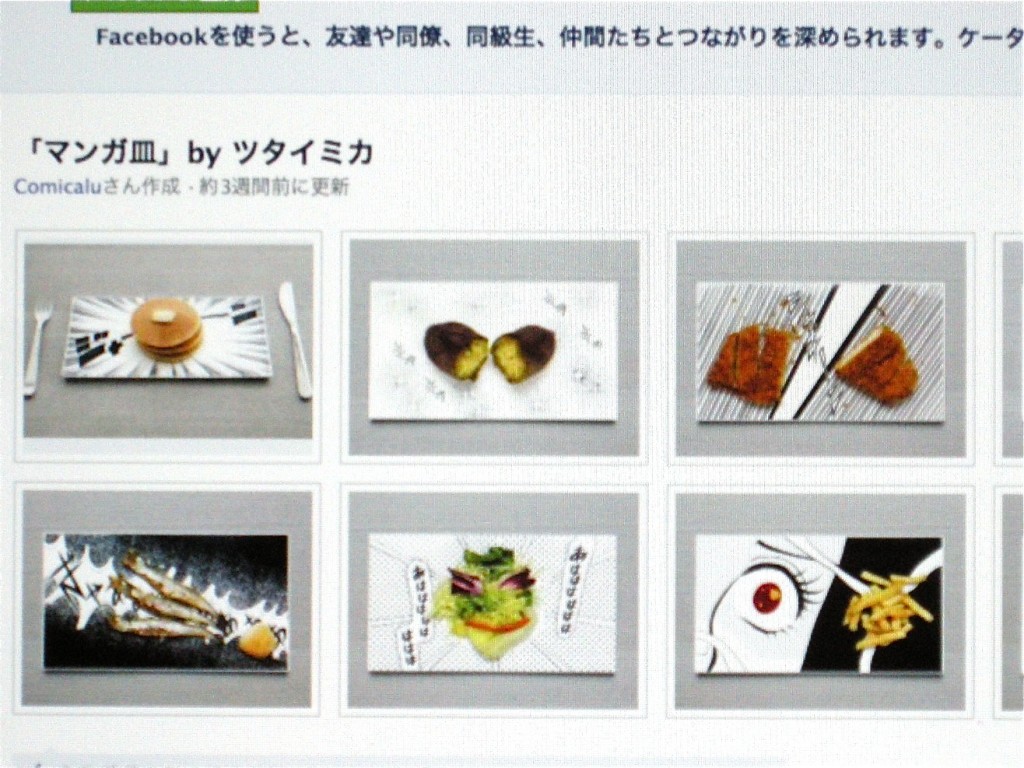昨日観音森に登ってきました。鳥海山は西側の裾が日本海に没していますが、庄内平野のほうから見て西鳥海(笙ケ岳)から左に長くなだらかに続くスカイラインの途中に、きれいな三角錐の小峰が見えます。他のところはすでに森林限界よりずっと下なので樹々に覆われて山肌が黒っぽく見えますが、その三角形だけは冬期間はほぼ真っ白になるで、大きさのわりにたいへん目立ちます。これが観音森です(古文書には桑ノ森とも)。
標高は685.2mで、何万年も前にできた火口丘=溶岩ドームです。西側の急な斜面は標高差300mもあります。比較的粘度の高い溶岩だったらしく、むくむくと盛り上がったまま固まったものとみえます。この観音森の約1.2km東側には猿穴という噴火口の跡があります。直径は100mに満たない小さなものですが、ここから流出した溶岩はかなりの量で、先端は海まで達しています。女鹿から三崎・小砂川沓掛海岸にかけての急崖がそれです。つまりわりあい標高の低い、狭い範囲に凹=猿穴と、凸=観音森という火山性の地形が観察できるわけで、その意味でもたいへんおもしろいところです。
私が観音森の頂まで登ったのはもう40年も前の冬のことで、今回が2回目ということになります。冒頭にのべたように非常に目立つピークなのでぜひまた登りたいとは思っていたのですが、かつての歩道(参詣道の小砂川道)はほぼ完全に廃道になっていて、もし無雪期に登ろうとすれば猛烈な薮こぎを覚悟しなければなりません。一帯は農耕に牛馬を飼っていた時代には採草地だったそうで、そのため大きな樹木こそ生えていませんが逆にそのぶん灌木や竹などが密生しているというわけです。それでもし頂上まで登ろうとするならブッシュが雪に覆われた時期、しかも積雪がある程度しまってきて、天気も猛烈な吹雪などにおそわれる心配のない時期にほぼ限られてしまいます。2〜3月中旬というところですかね。
私が昔観音森に登ったときは小砂川の駅からえんえんと観音森林道を歩いたのでたいへんでしたが、今回は頂から直線で北西約1.5km麓にある観音森の集落までは自家用車で入ることができました。そこからははじめの1/3くらいは林道を歩き、あとの2/3は地図で地形を読みながらの登行です。前は西側斜面からのほとんど直登でしたが、今回は北側からです。もちろんルートはすべて雪上のため、最初から最後までカンジキをはいて行きます。
さいわい天気も晴れて見通しがよく、しかも1週間ばかり前のものと思われる誰かのカンジキの跡もだいぶ残っていたので、迷ったりすることもなくスムーズに頂上まで達することができました。ただし頂上直下の急斜面はクラスト(雪面が低温と強風で凍結状態になること)していたので、ピッケルでステップを切りながらの登行となりました。写真の右側の稜線です。正面からの直登は最後がそうとう急斜面なので難しいと思います。もっともアイゼンやピッケル、ザイルなどのフル装備であえて挑んでみるのもいいかもしれません。
観音森頂上からはさえぎるものがいっさいない360度の絶景。東側には稲倉岳や新山らしい鋭いピークも頭をのぞかせています。日本海や庄内平野ももちろん一望のもとです。頂上一帯はあまりにも風が強いので積雪は30cmくらいでしょうか。標識もちゃんと確認できました。
上りが約2時間半、下りが1時間弱の、たいへん快適な楽しい山行でした。猿穴にも行きたかったのですが、時間的にあまり余裕がなかったので、今回はパス。それに猿穴のほうはすぐ近くまでいちおう林道が通っているので(かなり荒れていて廃道同然ですが)、ここには春から秋まで以前に何度か訪ねたことがありましたから。