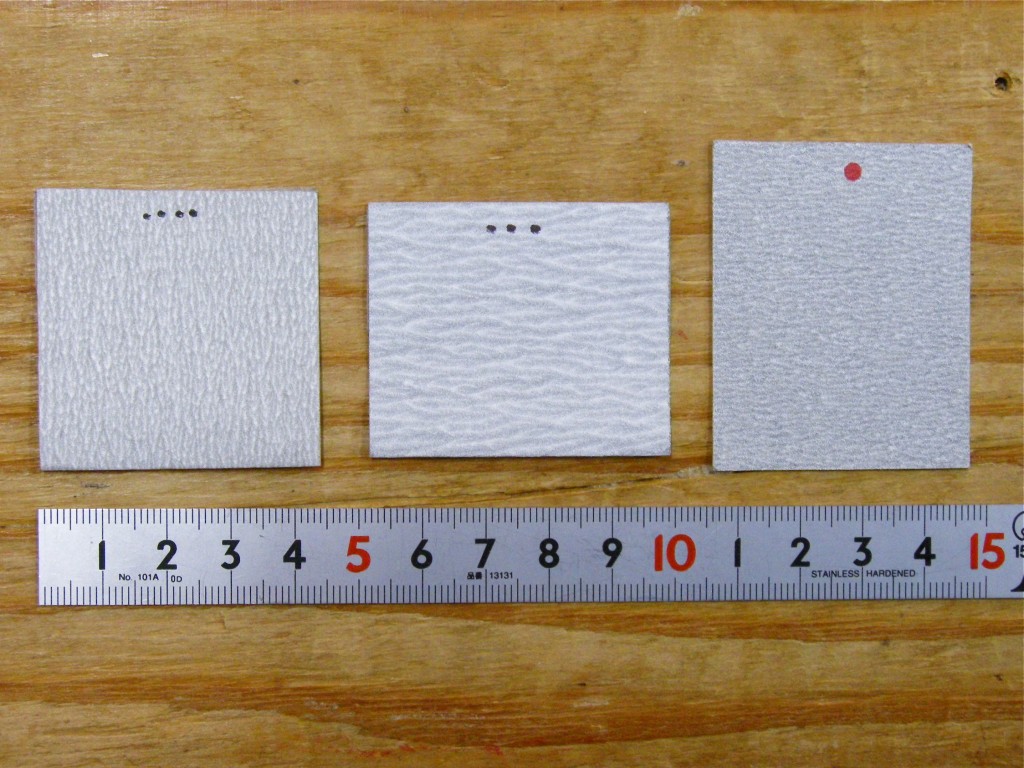朴落葉ちいさき骸にかぶさりぬ
ホオノキ(朴の木)は一枚の葉としては国内で最大と思われる大きさの葉を有する落葉広葉樹。長さ30cmくらいはむしろ小さいほうで、40cm半ばに達するものさえある。名前自体がその大きな葉を昔は食べ物を包むのに用いられたことに由来するらしい。花も国産広葉樹では最も大きく、春に枝の先に直径15cmほどの白い芳香花を上向きに開く。樹高20〜30mにもなる高木なので、よほど大きな屋敷でもないかぎり庭木には不向きなのが惜しい。幼木の、細い幹の先にパラソルのように開く若葉の姿もじつに美しいのだが。
太陽をおおかた周り十一月
地球は太陽のまわりを半永久的にぐるぐる回り続けているので、実際には始点も終点もないのだが、いちおうは年のはじめの1月1日を起点としよう。さすれば十一月半ばともなればもう1周分のあらかたを回ってしまったわけである。地球と太陽との距離は約150000000kmもあるので、地球は1年間にその2πrの約900000000kmも動いていることになる。すなわち時速100000kmくらいの猛スピードで太陽の回りを駆け巡っている計算だ。驚いたね。
廃線のどこまでも平行線や雁渡し
私はいわゆる「鉄っちゃん」(鉄道マニア)ではない。が、山登りの際などにその麓でときおり鉄道の廃線にでくわすことがある。それは正規の公共鉄路であったり、土木工事や原木搬出のための軽鉄道の跡だったりするが、いずれにしても栄枯盛衰、感傷をさそうものではあるな。赤く錆びついたレールをどこまでもたどっていけば不思議の国へたどり着きそうな空想にかられたとしても無理はない。/雁渡しは雁(ガン)が渡来する初秋から仲秋にかけて吹く北風のことで、別名青北(あおぎた)ともいい、秋の季語である。もともとは船乗りや漁師などから使われるようになった言葉だというのだが、雁そのものを近頃はあまり見かけなくなったような気がする。