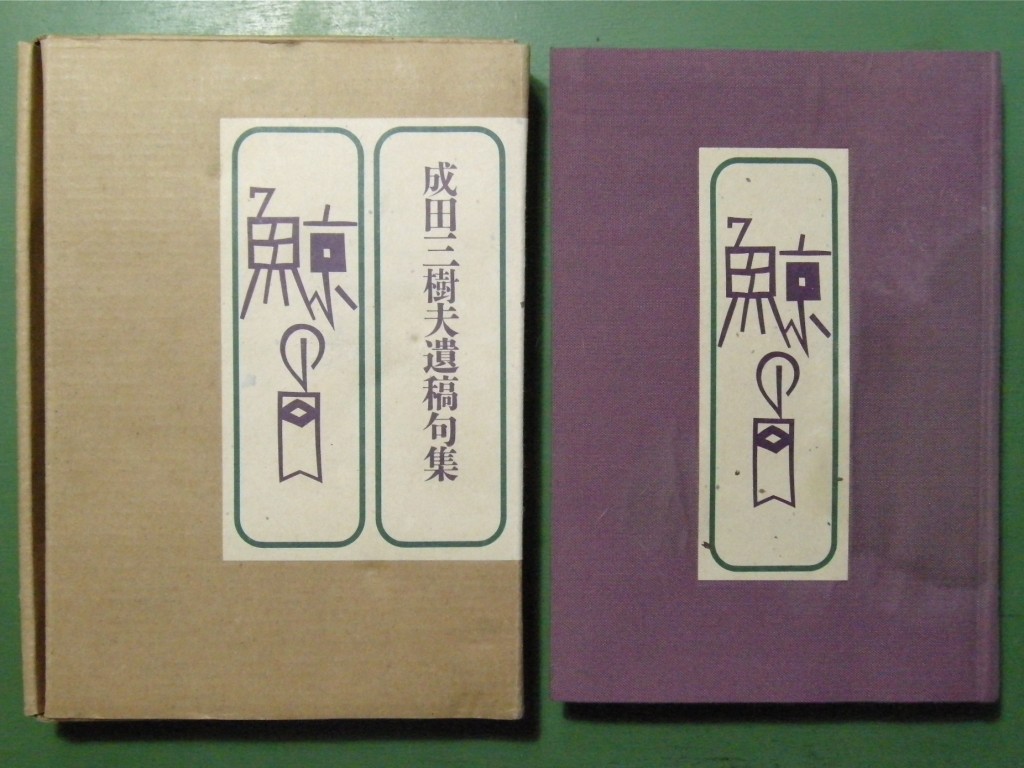当工房の旧ホームページは、2004年3月から2009年1月まで発信していました。その後パソコンの新しいOSがそのホームページ作製ソフトに非対応となってしまったので、現在はワードプレスというソフトを使ってブログ形式で発信しています。旧ホームページはこのサイトの各ページ右側の「リンク」の覧で「(旧)ホームページ」という部分をクリックすると閲覧することができます。
さてその旧ホームページですが、その中に「ティーブレーク」と名付けた覧があります。最初のページの下方で最後の項目として置いてあるものです。当サイトは基本的には木工房オーツーのホームページなので家具や木製小物などの発表や宣伝、木工の技術や機械道具や材料などのお知らせを主とするサイトなのですが、そればかりでは木工をされている方以外の方にはあまりおもしろくないかもしれません。そこで、私の仕事外の取り組みだった俳句を中心として、自作の句2〜4点と句中の言葉や句にちなんだことがらの解説などのミニエッセイを添えたページをときおり発信していました。こちらは自作の句数計387句、ページ数で計142頁となります。上の写真は最後のページ=179頁を印刷したもので、[リカちゃんは正座が苦手雛飾]という句を末尾に載せています。
前のホームページは、通常のパソコンの画面で縦スクロールすることなく一度に見ることができるページをそのままA4サイズでプリントアウトすることもできるようにしていました。したがって書籍や雑誌のページのように字数などは基本的に固定です。レイアウトも崩したくないので、テキストも含めすべて画像で出力しています。ただこのようなスタイル、自分で作った俳句2〜4点に、ミニエッセイをくわえ、さらに自分で撮った写真をそえて限定された大きさのページに過不足なく毎回きっちり納めるのは、けっこうな難事でした。
しかしながら、この「ティーブレーク」をご覧いただいた方の中で少なからぬ方から、俳句と短文と写真のマッチングがとても個性的だし内容もいいとのありがたい評価をいただきました。句作のほうは仕事の関係やその他諸々の事情もあって、ホームページへの掲載が頓挫するとほぼ同時にかなりトーンダウンしていたのですが、最近またひょんなことから句作を再開し、また近在での句会への参加を要請されています。
これをいい機会として当サイト上で「ティーブレーク」のようなものを近々始めようと考えています。同じ名前ではなく別の名前とも考えたのですが、まあこのへんは適当にということで「コーヒーブレーク」とでもしますかね。芸はないですけど。