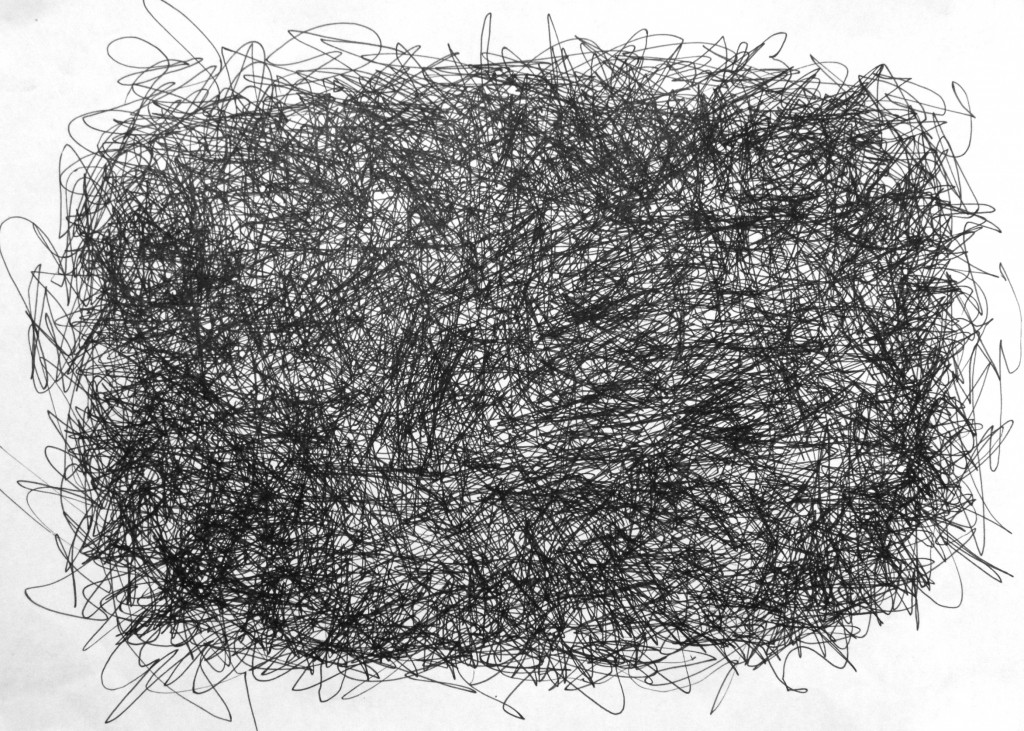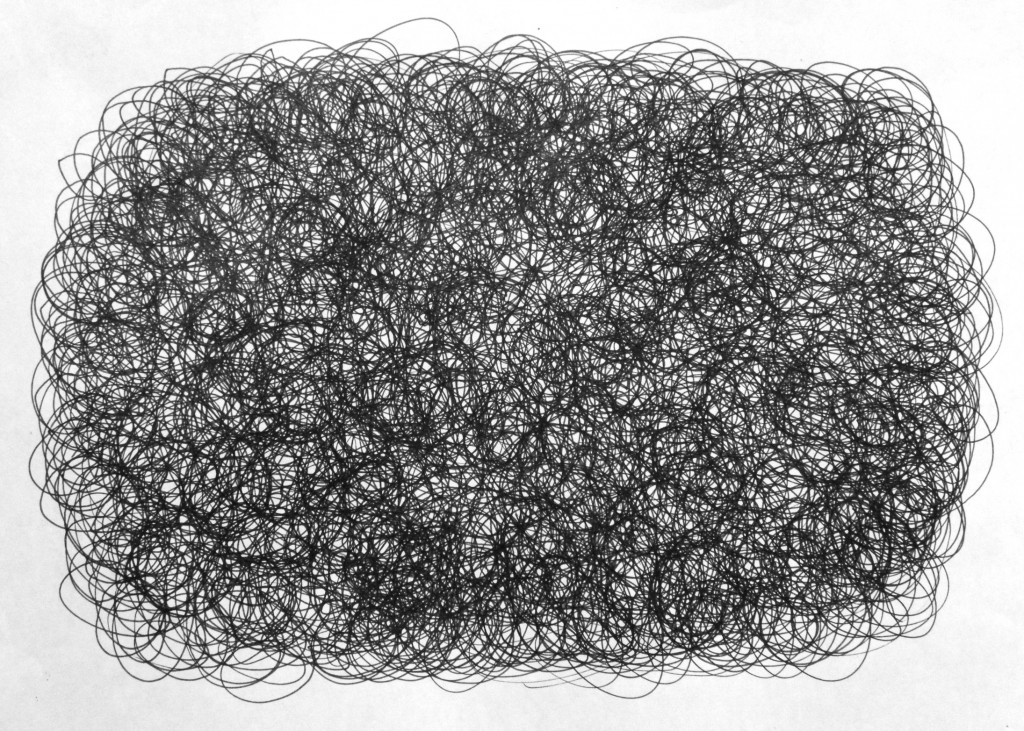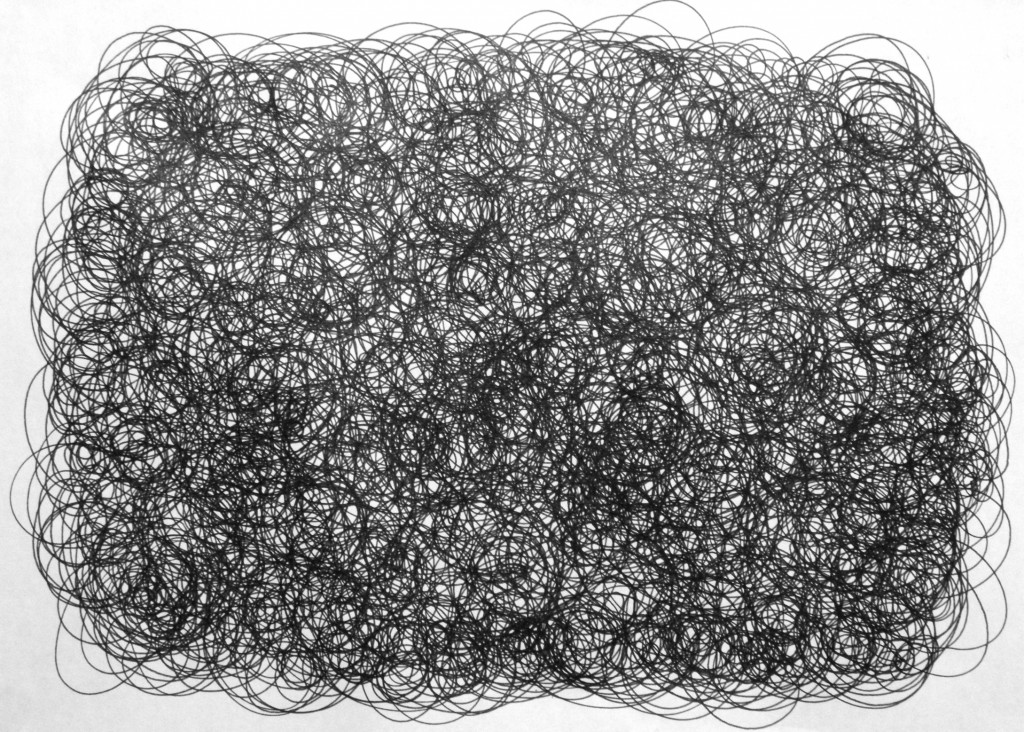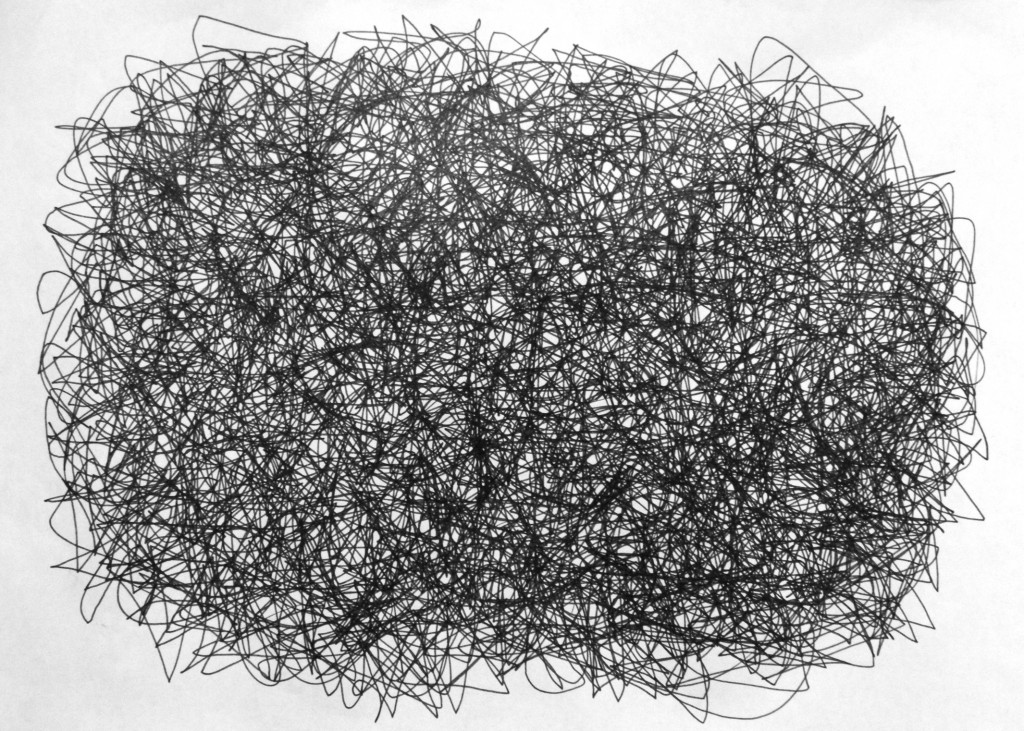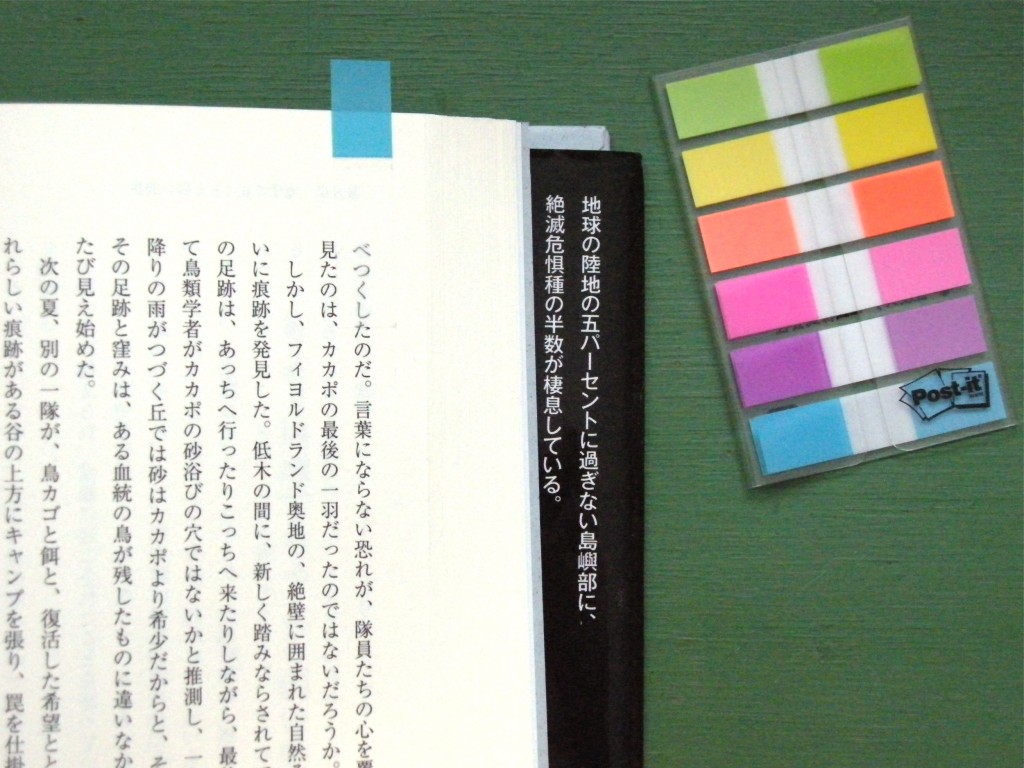マキタの最新型のインパクトドライバです。電源は汎用形14.4VのリチウムイオンバッテリーBL1430。マキタのインパクトドライバは以前から持っているのですが、昨夏のリフォーム工事で若い大工さんが使っているドライバがいい感じだったのと、前の機種がすでに9年間かつ相当頻繁に使っているので、そろそろくたびれてきたかなということで新調しました。
下の写真は上が旧来の機種で型番はTD130D、下が今回の機種で型番TD137Dです。ということはすでにこの10年ほどの間に7回モデルチェンジしていることになります。とくに木工事ではだいぶ前からですが、釘打ちではなくネジ止めが圧倒的に主流となっているので、それに必須の電動工具である充電式インパクトドライバはメーカーの目玉商品。マキタや日立・パナソニック・リョービ・MAXなどがしのぎを削っています。
マキタのうたい文句ではこのTD137Dは世界最短&最強とのことですが、ちなみにTD130Dとどれくらいの違いがあるか比べてみましょう。左がTD130D 、右がTD137Dです。
電動機 直流マグネットモーター 直流ブラシレスモーター
回転数 0〜2400回転/分 0〜1100、2100、3400回転/分の4モード
打撃数 0〜3200回/分 0〜1100、2600、3600回/分の4モード
締付トルク 最大140N・m 最大170N・m
質量 1.4kg 1.3kg
機体寸法 146×79×235mm 119×79×238mm
スペック一覧だけではわかりにくいですが、まずモーターがカーボンブラシのないモーターに変わりました。そのぶん機体の全長が28mm短くなっていますし、そうそう減らないとはいえカーボンブラシの交換も不要となりました。
それから回転数・打撃数が4つのモードから任意に選択できるようになったことです。これまでもスイッチの引き加減で無段階でそれらを変えることができたのですが、微妙な加減はむずかしく、とくに小さなネジなどを締める場合はつい締めすぎてしまうことがあります。その点、あらかじめ最大値を設定できるのでその心配が少なくなりました。弱・中・強のほかに「テクスモード」もあり、テクスネジを締めるときはこのモードを選ぶと途中までは速く、締め付けが始まると自動でゆっくり締めることができるように変わります。テクスネジはネジ自体が自分で鉄板などにネジを切りながら締め込んでいくしかけなので、規定以上に強く締め込むとネジ山がこわれてしまうからです。これらのモードは機体下部に赤いLEDで表示されます。
締め付けトルクは170ニュートンまでアップしています。機体が小さく軽くなったのに逆にパワーは増大しているわけで、実際使ってみると100mmとか125mmなどの長いコーススレッドも楽々締め込むことができます。もちろんブレーキが付いているので、スイッチを離すと回転はすぐに止まります。
手元照明は以前は回転が始まると自動で点灯し、回転が終わると10秒くらいで自動で消えるのですが、新しい機種ではON/OFFやONのままを任意に選ぶことができるようになりました。明るい箇所では照明は不要ですし、反対に工事用照明を別に用意するほどではないものの、実際に打ち込みする前にもすこし明るさがほしい場合は重宝します。
上記の4モードならびに照明の選択は機体下部のスイッチパネルのボタンを押して行うのですが、そのパネルには充電池の残量も3段階で表示されるので便利です。3つのランプのうちの一つが消えると残量半分とのこと。
機体の色は4色あって自由に選べるのですが、それも数ある電動工具のなかでもだんとつに需要があり人気があるからです。私は今回はいちばんしぶいブラックにしました。いかにも本職の道具という雰囲気でかっこいいですね。ホームセンターなどで売っているインパクトドライバに比べると最大4倍くらいの値段差がありますが、じゅうぶんそれだけの価値があると思います。