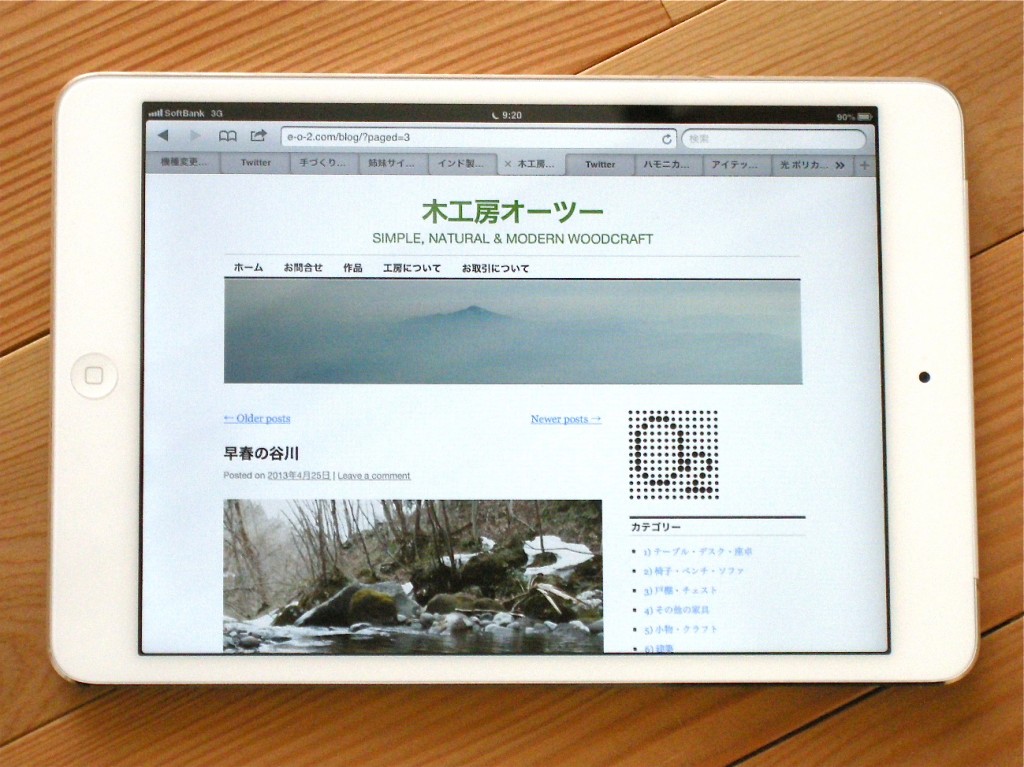5月5日に一人で登った出羽山地の経ケ蔵山(474m)ですが、じつはこれまで十数回登った中で今回が初めてという体験がありました。それはメインルートから逸れたところにある「胎内くぐり」のルートをたどったことです。
比較的里に近い急峻な岩山ではしばしばあることですが、経ケ蔵山も昔は修験道の鍛錬の場でもあったわけです。で、その大岩や崖にすこし異形のものがあるとなにかしら曰くのある名前をつけ信仰の対象としたり、鍛錬する際の里程標とします。胎内くぐりもそのひとつで、大岩の狭小な隙間を半ばむりやりくぐり抜けていくことで、俗世の穢れを落とす、または生まれ変わるとみなすのですね。はっきり言えば女性器や産道をイメージしているわけで、岩の形状がそれに似たものであればあるほど崇敬されるでしょう。
これまでも胎内くぐりの道標を目にするつど気にはしていたのですが、子どもや他の人を連れての山行が多かったので、ただでさえ急な道で難儀しているのにこれ以上の負担はという理由で避けていました。今回は単独行で天気も薄曇り、やや肌寒いくらいの陽気、薮もまだあまり繁茂していないという絶好の条件だったので、猿渡りを過ぎたすぐあとの分岐を右に入っていきました。道形はわりあいはっきりしているものの転げ落ちそうな急斜面を何百メートルもトラバースしていくので要注意です。初心者はやめたほうがいいでしょう。まあ誰でもそう簡単にアプローチできたのでは鍛錬にはならないでしょうけど。
写真はメインルート上の猿渡り、胎内くぐりの看板、入口、穴、くぐり抜けてから(中央下の暗がりがその穴。花はユキツバキ)、やや離れたところから見下ろし(胎内は中央奥の斜上する岩の下)です。「産道」は人ひとりがなんとかやっとくぐれるくらいの大きさで、下は土の急傾斜なので補助の綱(電気コードを代用?)が張ってありましたが、例によって私はこういったものはアテにしないで自力で這い上がりました。そのあともメインルートにもどるまでさらに200mくらい急な道を登ります。最後の写真は経ケ蔵山の頂上から見た胎蔵山(729m)です。この山にもしばらく行ってないな〜。