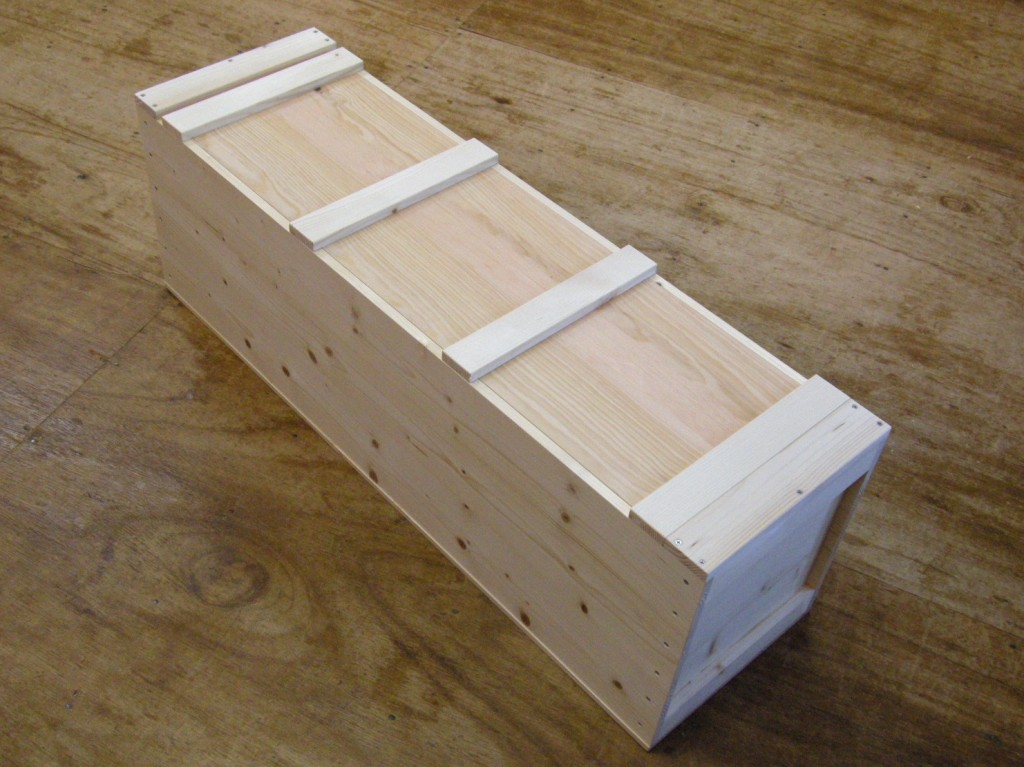5月19日、高校の特別授業の下見で鳥海山の高瀬峡に下見に行きました。車道終点の山ノ神の駐車場からだと、遊歩道のいちばん奥まで往復しても正味1時間半くらいですが、道すがらいくつもの滝に出会うことができます。順番に写真をかかげてみます。
高瀬峡一帯にはもっとたくさんの滝があるのですが、ふつうに遊歩道を歩いていて簡単に見ることができるものに限定です。それらの滝は湧水起源のもの、湧水と雨水が混じっているもの、主に雨水起源のものなど、水源はいろいろですが、いずれも鳥海山に降る膨大な雨雪が大元になっています。
第一吊橋をすぎて間もなくの遊歩道分岐を右にすすんで行くと最初に出会う滝で、ヒノソの蔭ノ滝。くの字の斜めの滝ですが、主に雨水起源です。水量の増減が激しく、冬は雪に閉ざされてしまいます。
第二の吊橋に向かって急斜面を斜めにおりていく途中で、スギ木立の間から左側にみえる滝で、バンバ沢の由蔵滝(よしぞうだき)です。これの滝壺は婆様淵と呼ばれており、姥捨伝説があるとか。湧水と雨水が半々くらいに混じっています。
バンバ沢にかかる吊橋(遊歩道の第二吊橋)のすぐ上流に見える滝です。落差は5mくらいかと思います。
吊橋を渡り、次いでやせ尾根に上がってその尾根をすこし南下していくと擬木の柵があります。そのあたりでアカマツやミズナラなどの樹間ごしに直下に見える滝で、バンバ沢の薬師滝です。下部は直瀑になっています。
長大な急斜面をジグザグに下りていくと、沢の対岸岩壁にかかる滝が正面に見えてきます。カラ沢に落ちる剣龍ノ滝ですが、岩盤(地層)の境界線から吹き出す湧水100%の滝です。右側の小さな滝も同様に湧水起源のもの。写真右隅に見える流れがカラ沢の本流です。
遊歩道はカラ沢の谷底で渓流にそって上流に続いていますが、 株立ちのサワグルミの大木をすぎると、やはりカラ沢の対岸に見える滝があります。白糸ノ滝です。これは主に雨水起源で、初夏以降で晴天が続くと涸れてしまいます。
最後は真打ちといいますか、カラ沢本流にかかる大滝です。節理が発達したオーバーハング気味の断崖絶壁を水がまっすぐ落ちています。雨水と湧水とが混じっていますが、平均すると雨水の比率のほうが高いようです。ただ厳寒期でもアイスフォールになりこそすれ、完全に落水が止まることはありません。写真の右下の落水はごく小さなものですが湧水です。