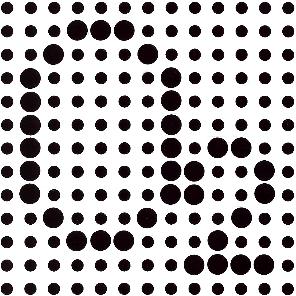酒田市出身の小説家・俳人である佐藤四郎(1911~1941)の句集『鳶』である。明治末に生まれ、大正、そして戦争の始まる直前の昭和16年7月までという、わずか31歳の短い生涯だった。父佐藤良次は上田秋成を世に出し、兄の三郎はジャーナリスト、弟の七郎は本間美術館学芸員という、いわば文化人一家のなかの一人である。国学院大学の卒論は父の遺志を継いだ「上田秋成の文学」であったという。
しかし腎臓病をわずらい酒田市に帰郷。地元の若手の詩人等からなる文芸雑誌『骨の木』に加わり、俳句や随筆・小説・評論などを発表している。『骨の木』は郷土史家・随想・川柳作家でもあった佐藤三郎、グラフィックデザイナー・詩人・俳人であった佐藤十弥が中心となって戦争前夜から戦中にかけて(昭和10〜18年)酒田で発行された雑誌で、30号で終巻となっている。
句集『鳶』は昭和14年(1939)に発刊されたもので、100句が収録されている。和綴じ100部限定というぜいたくな作り。『骨の木』に「蕪村の浪漫精神」という評論を載せているのだが、彼の句にはたしかに蕪村の空気が流れているように思う。それから期せずして、当ブログの8月25日に載せた村上鞆彦の句(句集『遅日の岸』)にもよく似た感じがする。
形式としては伝統的な俳句スタイルを終始ふまえつつ時代的現代的な素材にも意識はおよんでおり、写実を基調としながらも、静謐な描写のかげに虚無や悲哀・諦念をにじませている。「神は細部に宿る」なる箴言を想起するような、自然現象のじつに微細であえかな部分にも目をこらす一方で、空や海などの大きな景もよく出てくる。格調が高く完成度はなかなかのもの。この句集が句歴10年程度の成果であることを思うと、句友であった佐藤十弥らの「夭折した希有の才能」という評価もおおいにうなずけるものがある。
以下にかかげた20句は、シテの会のメンバーであり先輩である相蘇清太郎氏がようやく探し出した句集『鳶』を拝借し、私が書き写したもの。このような質の高い句集に、しかも地元でめぐりあえてたいへんうれしい。
ゆきげ川雪よりおそく雲も流れ
つくし野のつきれば川のあふれをり
手巾につくしをおけば粉のみどり
病む人の雛飾らせてねむりけり
鳩時計とまりてながき春の晝
菜の花の三里を汽車が截つてゐる
潮退けば海盤車一つに濱ひろし
くづれしや闇の牡丹の香みだる
掌の闇に螢息づく光かな
蚊帳ぬちと見しを螢火流れさり
ゆくかたは海と見えしを大揚羽
夏眞晝ひとなき街を白き蝶
闇を截る玻璃戸に貼りて蛾は白し
蠍座の尾に帆船の睡りけり
小春日や虻酔ふてゐる菊の蕊
凍港となる夜オリオン眞青なる
涯昏き枯野を鷲の狙ひ翔ぶ
冬木立星座を懸けて野に隣る
鳶ゆれぬ吹雪とどかぬ街の蒼天
星闇や谿々雪崩れ響みたり
(追記:佐藤四郎のこの句集は80年近く前のものでありながら、まったく古くささを感じることはなく、現代の句集といわれても同意してしまいそうである。ひきかえ最新の句集である村上鞆彦の句が、80年前の佐藤の句とさして変わらないというのはかなり問題なのではないかという思いを私は強めている。)